今年もいよいよ終わります。年末年始は寒波で雪みたいですね。来年はどんな年になるでしょうか。
とりあえず脇腹を治さないと・・・(12/31)


寒波の襲来にむかって行ってきました。木立を抜けて直登になるあたりはいつも風が強いので当然予測してたのですが、いや〜、ここまでとは想像して、ましたけど。ふらふらよろよろで、まともに歩きにくい。頂上ではほとんど立ってられないほど。みんなしゃがんでました。早々に久住別れの避難小屋へ文字通り避難し、そこでお昼。次に向かった扇ヶ鼻付近は特に樹氷がきれいでした。西千里ヶ浜から沓掛への途中は、豪勢な霜柱の上をさくさくと歩いて気持ちよかったです。そういえば沓掛のところにある温度計はマイナス9度を指してました。山頂はも少し低かっただろうし、それにあの風、寒かったはずです、ぶるぶる。(12/15)






もう少しもちそうだ、というサザンカ情報が入ったので急遽行くことにしました。幸い天気もよさそうだし。そういえば昨年は3回も行ったのに今年はまだでした。久留米、甘木、田主丸方面がきれいに見えました。花はだいぶ散って盛りは過ぎていましたが、大丈夫、きれいでした。じつはここのサザンカが咲いているのを見たのははじめてでした。若宮八幡宮の狛犬さんたちもなかなかでした。穏やかなのんびりとした一日がすごせました。
それにしても道がわかりにくいですね。振り返ってみると「あれ、登るときはこっちじゃなかったよな」みたいなのが何カ所かあるし。(12/5)









国東半島の山です。地塁と言ってこの辺りに多いんだそうですが、両側が絶壁になった狭い鋸歯状の尾根を歩きます。楽しくないはずがない、ですね。ただし天気の良い日に限ります。なぜって、考えるだけでも恐ろしいと思いませんか?もちろん見晴らしは抜群。豊前海、別府、高崎山、由布岳、鶴見岳などが一望です。なぜかキクをたくさん見かけました。しかも、薄い黄、濃い黄、白、薄紫とバラエティーにとんでいました。
そうそう、目の前で眺めただけで、ピークには立ちませんでした。狭いところに人がいっぱいで、待ってる人もいっぱいで。なかなか降りてこないし。だから・・・ (11/27)











大山入口のバス停をスタートして、大山教会を目指して歩き始めます。これだと思って一つ早く曲がってしまい引き返し20分ほどロス。少し先にちゃんと標識がありました。で、1時間ほどで大山集落にある教会に到着。かなり高いところにあります。さらに10分ほどで、民家の横にある登り口へ。その家の人に「竹やぶになっていて道はなくなってるんじゃないか、かなり登りますよ」と言われた。登り始めると、なるほど、いきなりめげそう。やめようかな、なんて気持ちがよぎります(やめるはずはないですけどね)。道がほとんど喪失状態、それに急な登り、でも短い間隔でテープがあり迷うことはありません。尾根に出ると防火帯になっている。これがまた・・・ もちろん道幅はあるのですが、急な登りが多くて、まるで上級者コースのゲレンデを直で登っている感じ。きたわれます。熊ヶ峰に到着。展望は全然ない。さっさと悪所岳へ向かう。こんどはなかなか快適。時折海が見える。頂上は岩になっていて非常に狭く、サカキやへんなサザンカ?などが周りに生えているがそこそこ展望はある。気持ちがいい。さあ次は戸町岳。途中目をつけていた場所でお昼を食べ、分岐まで引き返す。分岐の標識には戸町岳の名がない。じつはその後も、あるのは烏帽子岩への標識ばかりで最後まで戸町岳の文字はなかったのです!なんで?とりあえず途中までは同じ道を通る烏帽子岩への道標に従って歩き、あとは勘頼りで、適当なところで逸れて、無事到着、やったー!今回一番見晴らしがいい。長崎市街、雲仙方面が見える。天気もいいし、よかったよかった。で、帰りは大山教会の下の方に出ました。
(11/24)












活水のあるオランダ坂をのぼりきったところで東山手の方へ降り、Uターンして登り返し、今度は丸山、思案橋へ向かって、狭い坂の道を降りていき、浜の町アーケードを通って眼鏡橋あたりへ。なんども歩いたことのある道です。それから30年前に行ったっきりのジャズ喫茶マイルストーンの場所を確認。夕食後に行ってみる。浜の町のBunBunはその後も何度か行ったことはあったのですが、マイルストーンのマスター(二代目)によれば、今は既になく建物自体がないということです。小さなおばあちゃん、いや、小柄な年配の女性がされてたジャズ喫茶で、いい店だったのに淋しいことです。だまってちょこんとスツールに座ってあったのが印象に残ってます。
中島川(眼鏡橋が架かっている川です)の東側にはずらっとお寺が並んでいます。その後ろは山の斜面でそこが墓所になっています。むかし、その斜面を南から北へずっと歩いていったことがあります。気持ちよかったです。缶詰の元祖のお墓がありましたよ。(11/23)









今年も行ってきました。ちょっと早すぎではありましたが、さすがにきれいでした。息が詰まるほど見事です。もちろん狛犬君たちにも会ってきました。相変わらずカッコよかった。しかし、とにかく人が多い。わんさかわんさか貸し切りバスでもやってくる。テントがたち露天が並ぶ。九年庵の公開が終わって改めて行こうかな、静かになって。そしてゆくり歩いてみるのもいい。城原川沿いや、白角折神社あたりとか。
先日の黄砂が嘘のように空気が澄んで山が近くに見えていました。
(11/18)












南峰から大鍋小鍋を経て雨ガ池に降りる予定だったのですが「通号止め」。仕方なくそのまま小鍋を巻いて北峰に登り、それからいったん下り、そして再び本峰に登り返しました。鞍部からから見上げた本峰の高かく見えたこと。アップダウンの繰り返しはきついですね。しかも急だし。
朝は曇り。ガスもありましたが、しだいに晴れてきて、気温は低かったのですが(スガモリ越の温度計は−4℃)、気持ちのいい山歩きとなりました。
(11/17)

樹氷

草氷?

こんなかんじ

坊ヶツル

林の中

え〜!

小鍋

大鍋

再び本峰へ

ジェイソン?

よく歩いたなぁ

黄砂

モネ?
トレイルの低山企画。王子宮〜北面〜高良大社〜南面〜高良山山頂〜森林公園〜王子宮のコースを案内しました。
(11/10)
逆光を受けて銀色に輝くススキを見たかったのですが、タイミングよく太陽が出てくれませんでした。でも、天気は穏やかで、紅葉もご覧のようにちょうど見頃。ゆっくりのんびりまったりと楽しんできました。そうそう、ススキの上に出たときに、「よし、ここまでくればもうあとは・・・」と思ってテープを見落としてしまい、しばらくうろうろしました。
バラはもちろんですが、じゃがバターもなかなかでした。
(11/7)














百道の向こうの方に可也山が見えます(写真1)。それから今年春に歩いた、篠栗から鳴淵ダム、JR山手駅付近の高架も(写真2)。
いや〜、ひどいめに合いました。ほうほうの体で帰ってきました。いやいや、バルーンフェスタのことではないのです。ついでにと、ちょっと足を伸ばして山へ行ったら、にっちもさっちもいかなくなって・・・ あ〜びっくりした。あ〜疲れた。だいたい今日はさいしょっからとんでもなくアホなドジをやらかしたし、よっぽどそういう日だったのでしょう。まいったまいった。
ずっと行きたいと思っていた柏岳、大変でしたが、登り口の円応寺にホトトギスが咲いていましたよ。いっぱい。
(11/2/10)


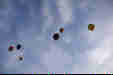











天気はあまりよくなかったのですが、眼下の雲と頭上の雲に挟まれた空間が何とも不思議な感じでした。
(10/30/10)






心配された天気はなんとかもちましたが、今回も眺望がまったくききませんでした。登りは緩やかでちょっと物足りない感じでしたが、下りは俄然面白くなりました。アスレチックみたいで、苦労しながらも「さあ、ここはどうやっておりようか」などと、遊び心の旺盛なおじさんやおばさん、いや、しつれい、おねえさんたちもおおいに満足のようでした。
(10/23/10)




目の覚めるような紅葉を見に行きました。でも、天気がご覧のとおり。アハハ・・・ というわけで、何にも見えませんでした。ちゃんちゃん。祖母山の紅葉を期待しましょう。
とはいっても、牧道にはマツムシソウなどがきれいでした。あんまり淋しいので載せておきます。
(10/20/10)

祖母(が見えるはず)

御池の紅葉

マツムシソウ

ウメバチソウ

小さな秋
久しぶりの古処山でした。山頂でお昼を食べて、大将隠し、奥ノ院まで足を伸ばし、ツゲの原始林の中を戻りました。レイジンソウを期待していたのですが、見当たりませんでした。でも、秋空の下、のんびり気持ちのいい山歩きでした。
小さなミズヒキが何ともいえずかわいかったです。
(10/15/10)

ジンジソウ

ナギナタコウジュ

奥ノ院

ミズヒキ

ジンジソウ
山頂近くまで車道が走っているので、30分ほどの歩きで登れるし、ということだったのですが・・・やはり世の中はそんなに甘くない。あちこち通行止めでなかなか駐車場への道に近づけない(梅雨時期の雨でどうやら崩れているようです)。やっと、「よし、この道だ」と進み始めるとすぐにまたしても通行止め。しょうがないので50分ほど歩いてやっとスタート地点のはずだった駐車場に到着。もう既に1時半。すかした腹を抱えて登りました。お昼を食べたのは2時半を回っていました。腹が減って目も回りそうでした。でも、お土産の尾道ラーメンはおいしかった。じゃこ天が入っていたらもっとおいしかったでしょうけどね。
意外なほど花がたくさん咲いていて、どの花も不思議と色に深みがあり、きれいでした。
(10/11/10)

アカタテハ

アケボノソウ

アキチョウジ

ユウガギク?

アキノキリンソウ

センフリ

ムラサキセンフリ

シュロソウ

リンドウ

コゴメグサ?

トリカブト

すっかり秋模様
あちこちでキンモクセイの香りを感じるようになりました。去年見つけてびっくりした甘木公園のキンモクセイを見に行ってきました。咲き始めていました。うちのは、昨年18日でしたが、さて今年は?
(10/6/10)


9月26日(日):御池
夕方御池ロッジに到着したあと御池田代方面(あすのルート)へ少し行ってみる。それから宿のうらを散策。



小雨の降る中、御池ロッジを出発。燧ヶ岳登山組と、燧ヶ岳のすそを巻いていく燧裏林道組に分かれます。ぼくは後者をまかされてしまいました。
最初はいかにも尾瀬らしく、木道の上を歩き、ナンタラ田代、カンタラ田代と名のついた湿原ががつぎつぎと現れます。渋沢温泉小屋と尾瀬ケ原の分岐で渋沢方面のルートをとると道は下り始める、木道はなくなり、鬱蒼とした樹林帯の中を歩く。すぐに現れる次の分岐で三条ノ滝経由で尾瀬ケ原へ行くルートをとる。三条ノ滝へは、荷物を置いてルートを外れからピストンで行ってきました。戻ってきてお弁当。平滑ノ滝を過ぎ、温泉小屋へ出ると再び湿原と木道。あとはだらだらと、いや、のんびりと見晴の尾瀬小屋を目指します。木道の付け替えをしてました。ご苦労様。
天候のことも考えると裏林道でよかったかも。それに、帳面消しみたいになにがなんでも山に登らないと、っていうのもね。いや違う、山があれば登らなければという強迫観念みたいかなと。はい、まけおしみです。ほんとは登りたかったんです。でも、今回、あとで「そっか」と思ったのです。




















今日は自由行動、一日をどう使うかなかなか難しく、どうしようかなとさんざん迷ったあと、沼尻(尾瀬沼)へ行くことにしました。沼尻からさらに20分ほど行って、尾瀬小屋まで引き返してきてお昼。回復気味だった天気は次第に下り坂、お昼すぎて間もなく雨が降り始めました。という訳で雨の尾瀬ケ原を、竜宮小屋からヨッピ橋、それから牛首分岐、そして至仏山の麓にある至仏山荘へ。うん、いい計画でした。
明日は晴れの予報なんですが、さてどうでしょうか。
















早朝4時半出発。ヘッドランプを点けて暗闇の中を登ります。しかも雨(え〜っ、晴れの予定じゃなかったの!)。急な登りにつけられた木製階段は恐ろしいことに手前に傾斜しており、すべる。次第に空が白んできて、天気も徐々に回復へ向かう。振り返ると尾瀬ケ原、燧ヶ岳(ぼくは登ってないけど)の姿が見えるようになる。至仏山の頂上付近は少しガスがかかっていたが、次第に青空が広がり始め、あとは快適な山歩き。オヤマ田代を経て鳩待峠へ。お昼にキノコうどんをいただく。ふ〜っ、満足。




















軽くやっつけるつもりで、歩き始めましたが、黒雲が出て来たなと思ったらほどなく雷と雨。到着する頃ようやくおさまり始め、最初はなんにも見えなかったのですが、しばらくするとご覧のように雲が晴れ始めました。雨具の上だけは持っていってたのですが。ズボンと靴はずぶぬれ。
まだ時間が早かったので、森林公園まで行って、おやつを食べながらくつろいでいる間にほぼ乾きました。
(9/20)

教訓:準備を怠るなかれ
今カトリック教会を見に行って来ました。ゆめタウンあたりから河川敷へ降り、サイクリングロードを大城橋迄行ったら橋を渡って、それから北上します。競技場のところから13キロくらいでした。まだまだ暑いですが気持ちよかったです。久留米に戻って、お昼に食べたお好み焼きがおいしかったです。楽しい店でした。
(9/19)


写真は葛の花、へ〜
急な登りに、急な下り、岩がゴロゴロで、楽な道なんてありゃしない。展望だってほとんどないし、鬱蒼と茂った樹木の中を、昼食の時間もろくに取らず、途中、すべったり、こけたり、ひっくり返ったり、ぶつかったり、つまずいて倒れたりしながら、ひたすら歩くこと9時間半。最後は暗くなって、ライトをつけても足元がよく見えないし、あ〜、うんざり。えっ、風呂なし!ビールは〜? まったく、来るんじゃなかった! なんてひそかにみんな思ってたりして。
(9/15/10)

由布岳

ミヤマシグレ

こんなとこ歩きます

ホツツジ

高塚へ

ETあらわる

平治・三俣

ハガクレツリフネソウ
(9/11〜12/10)




霧島がだめになって代わりに赤川ルートで久住山に登って来ました。好きです、このコース。
赤川荘のちょっと手前が登山口。歩き始めてまもなくして沢に出ると、久住が見えます。気持ちのいいところですが、ゆっくり休憩するには早すぎ。水はビックリするくらい冷たいし、帰りの楽しみにとっておくことにします。木橋を渡って、赤川温泉の源泉をすぎると、ちょっと苔むした日本庭園見たいな(大げさ?)雰囲気になり、そこをすぎるとやがて傾斜が急になります。雨による浸食等でずいぶん荒れているので足元に気をつけながららひたすら登ります。やがて樹林帯を抜け視界が開け、阿蘇方面がきれいに見えます。容赦のない急登と雄大な展望を楽しみながら岩を掴んで這うようにして登ります。やっと傾斜が緩むと山頂はすぐそこ。高度がぐいぐい上がっていくのが気持ちいいルートです。
(8/25)

阿蘇・久住高原

肥前ヶ城

トンボ

キノコ

葉脈
奥の院の方へ下りて、南面を高良大社の方へ少し歩くと、ひぐらしの鳴き声につつまれるところがあります。ちょっと神秘的でもあり、なんだか不思議な感じです。別の世界に分け入ってしまったような。
山の中では7月から鳴いているんですね。知らなかった。カナカナカナカナ・・・・・
(7/29)
沢の中で、きょうもひぐらしの声につつまれ、しばし暑さを忘れるひとときを過ごしました。そうそう、世間知らずの箱入り娘イヌにじゃれつかれました。やっぱり僕はイヌなんです。じつは尻尾もあるみたいなんです。
(7/30)
えーるピアの体育館で太極拳の練習中に、カナカナカナと聞こえて来たので、あ、ひぐらし、と思って耳を澄ませると。それっきり。たった一度の鳴き声でした。不思議。
(8/9)
8月2日:
1日の19:30の新幹線で名古屋まで、それからバスで立山駅まで移動します。なかなか眠れません。バスの中から月が見えました。なんか、「真夜中のカウボーイ」みたい、それとも、サイモンとガーファンクルの「アメリカ」の情景?。まだ暗いうちに着いて、空が白んでいくのをぼーっと待ちます。朝食を摂り、ケーブルカーで美女平へ。さらにバスを乗り継いで天狗平へ到着。室堂まではお花畑の中を歩く。室堂からみくりが池を経由して雷鳥平まで下り、別山乗越まで登り返す。これが結構きつい。たぶんいきなり2,400mからスタートしたためと、昨夜の寝不足のためだろう。やっと昼食にありついて休憩したあとは、剣山荘まで、雪渓をいくつか渡りながら、ゆっくりと下りて行く。

















前夜は畳二枚に三人。いびきの合唱の中、その前の寝不足もあり、とりあえず必要なだけの睡眠はとれたかな。剣山荘を6時に出て、いよいよ劔岳へ。一服劔、前劔など槍の穂先のような小さなピークを3つほど越え、カニノタテバイを経て山頂へ。見事な快晴、360°の展望。これ以上は望めないコンディション。ただただラッキーです。怖いのは下りですが、カニノヨコバイも無難にクリア。よかったよかった。
チョウやクロユリは剣山荘の周辺を散策した時見つけました。



























別山乗越方面へ、今度は劔沢経由で戻って行きます。そして別山、真砂岳、大汝山(3,015m)、それから雄山と縦走して行きます。別山の眺望が特によく、富山湾に能登半島、富士山も見えました。雄山に登ったら、あとは、室堂のみくりが池温泉まで下るのみですが、一ノ越までは小学生の団体が何組もいてたいへんでした。最後は、3日ぶり!の風呂を楽しみに歩きました。














いわゆる立山黒部アルペンルートを辿ります。室堂のターミナルからトロリーバスで立山の真下を通って、ロープウェイを乗り継ぐと黒部ダムです。それから扇沢まで行き、お昼をたべたらいよいよ帰途につきます。
全日程をとおして申し分のない天気でありがたかったです。ほとんど奇跡的。でも、今回のアルプスは今までで一番気温が高かったと思います。暑いと疲れますね。
家についた時は夜中の1時を過ぎて日付も変わっていました。おつかれさんでした。
最初の写真はみくりが池から見た富山市です。






月光仮面のおばさん

もうだめだ〜

夜明けの珈琲
山口県防府市にあります。全国から猛暑と熱中症のニュースが届くなかでの低山企画、予想どおりの、地獄の山行でした。躰中の汗腺から容赦なく吹き出し流れる汗。いや〜、ひからびてしまうかと思いました。まるでモズの餌のように。で、肝心の山ですが、さすが山口?、昨年の陶ヶ岳にも劣らぬ楽しい山、のはずです、季節さえよければね。
登山口のお地蔵さんたち、みんなビール、しかもエビスの缶を首からぶら下げて、「はやく下りておいで、ビールが待ってるよ」と言ってるようでした。
(7/24)





天気がよかった。暑かったです。はじめて暮雨ノ滝(くらぞめ)を見ました(いままで通り過ぎるだけでしたので)。涼しげでした。それから、あと、頭をひどくぶつけて、昼間から星を見ることができました。ったく・・・
あ、そういえば、立中山からは先頭を歩いていたのですが、鍋割峠からくたみ岐れへ向かう途中、いきなりウリボウに出くわしました。すっかりあわてまくって(向うがです)逃げて行きました。
ひぐらしの、カナカナ、カナカナ・・・という鳴き声がときおり聞こえてきました。もう夏も終わり・・・ じゃないよね。
(7/21)

ヤマアジサイ

暮雨ノ滝

ホトトギス

ミヤコグサ

ウツボグサ

ユウスゲ

オカトラノオ
復帰第一戦。梅雨明けの日。雲仙の三峰五岳のうち矢岳、高岩岳、絹笠岳が雲仙温泉を取り囲むようにしてあります。そのうちの矢岳と絹笠岳に登ることにしました。
まずは矢岳。久々の山歩きです。まだ元気。下りて来たら、地獄を通り抜けて原生沼を回って、つぎは絹笠岳。比較的傾斜が緩やかで歩きやすいのですが、なにせ梅雨明けの日の午後、むしむしむしむし。結構こたえます。下山したら車道をスタート地点の宝原園地まで戻ります。小地獄がちょうど中間あたりで底になり後半は登り。車道とはいえ結構高低差のある1時間ほどの歩き。「まだかな〜。あぢ〜よ〜! ふろはいりた〜い! び〜るのみた〜い!」
(7/17)







やっと、やっとお日様登場。で、ネジバナを見に行ってきました。やあ、久しぶりだね。今年も咲いてました。
だいぶ「薄皮」もはげてきたと思うんですが・・・ 胃は昨日よりよくなったので、ほっとしました。変わらなければいよいよ検査を覚悟をしていましたが。
あ〜それにしても、ついに53キロになってしまいました。ちゃんと食べてるのに。誰か肉をわけてくれ〜。
(7/6)


神野公園にピンクのヒツジグサが、雨の中、しっとりと咲いていました。きれいでした。シオカラトンボもいました。午後はのんびりとビールを飲みながらブルースの演奏を楽しみました。
(6/27)
霧雨の降る中、避暑地に行ってきました。連日の雨で水かさが増え中には入れない。晴れた日にまた行こう。でも雨もまたおかし、ですね。
(6/30)
思いもかけずキヌガサタケに出会いました。びっくりでした。どしゃぶりでなければ、雨の中を傘をさして歩くのも悪くありません。でも、ときにはどしゃ降りに遭うのも、いとおかし。
(7/4)

ぎっくり腰に見舞われる前の日、高良山に行ったのですが、中腹あたりの林道(車道)に出て歩いていると、ずっと先に犬を連れた人がいました。犬が立ち止まってこっちを見ています。ほどなく追いついて、挨拶を交わしました。犬は足の短いころころとよく肉のついた小型犬で、ゆさゆさと楽しそうに歩いていきます。飼い主は感じのいい年配の男性でした。「おたくを見かけたんで、喜んで、待ってたんですよ」なるほど、ほんとにうれしそうに、尻尾をふりふり、と言いたいところだが尻尾が無い。この犬、小さい頃に尻尾は切ってしまうそうです。「こら、そげん先に行っても、おりゃ付いていっきらん」青息吐息でした。車にも寄っていくので、このまえ轢かれて大怪我をしてしまったそうです。後遺症が残るかと思ったそうですが、大丈夫、そんな気配も見えず、元気いっぱいでした。ちゃんと気をつけろよ。心配です。
(6/11)
ヤマアジサイ、大好きです。ふつうの紫陽花は、ちょっと重たく感じてしまいます。最後の画像は杵島岳(2007)のヤマアジサイです。 やさしい色、というより、さみしい色、いや、遠くを見つめる色だ。そう、ワイエスが描いた、クリスティーナの部屋のドアの色・・・
(6/2)




志摩半島のふたつの山を登りました。とくに立石山は僕が一番好きな山です。海抜ゼロからスタート。登り始めて間もなく芥屋の大門が見えるようになるとあとはピークに上がるまで素晴らしい展望を楽しみながら登れます。最高です。岩が露出して急坂ですがステップがはっきりしていて意外と登りやすい。
一方、可也山は糸島富士とか小富士とか呼ばれています。ピークからちょっと西に行ったところが展望がよく、玄界灘、福岡市街、唐津方面などが見渡せます(三角点はちょっとさみしかった)。やっぱり海が見える山はいい。
それから、若い人が結構登ってました。「噺家」さんとか「ミニベロ」さんとか、「さっき下りてませんでした?」「二回目です」さんとか。
そうそう、この辺りでは甲貝という貝がとれるそうです。殻を割って中を取り出したあと,スライスしてわさびと醤油で食べるとおいしいんだって。今度はわさびを持って行かなくちゃ。
タツナミソウがとてもきれいな色をしていました。白いタツナミソウがあるそうですが、まだ見たことはありません。
(5/29・30)

タツナミソウ

ナルコユリ

カタツムリ

亀の首から

糸島富士

亀の背から

ハマヒルガオ

亀の頭

待宵草

立石山

ウミガメ
てるてる坊主の威力には驚きました。はやければ午前中から雨を覚悟していたのですが、見てのとおり、なんと青空も見えるいいお天気。結局、下山完了と同時に降り出すというタイミングのよさ。殆ど奇跡的でした。
西峰へは溶岩壁の急登。そこからお鉢巡り:広い斜面を北に取り、東に向きを変えて下り、第4火口壁、第3火口壁の岩稜・岩壁を越えて剣ノ峰に取り付き、壁を攀り、巨石のブロックを渡り、乗越していく。鞍部に出たら南に巨石を越えて、灌木帯を過ぎると東峰に到着。
東峰でお昼を食べているうちガスが急速に上がってきてパラパラときたので、早めに下山開始、と思ったら、両足がつり動けなくなった人がでるというアクシデントがありました。が、なんとか無事全員歩いて下山、よかったよかった。
「おお歩いてる」のピークが剣の峰で、後ろは右から鶴見岳・馬の背・鞍ヶ戸です。
途中、倉木山がきれいに見えます(画像)。登り始めて間もなくドーンと最高の由布岳が見えるところや、狭霧台、タクシーを待ったところも。
(5/22)

さすがです

倉木山


おや、虹が


まず西峰

おお、歩いてる

東峰を望む

巨石

東峰も間近
 来し方
来し方
バイカイカリソウ

エヒメアヤメ

フウロケマン

キスミレ

イワカガミ

(5/18)

ユキザサがいっぱいでした
(5/19)
篠栗から、車道と時に遍路道を歩いて飯盛山をまくように、五塔の滝から鳴淵ダム横を通り、さらに南蔵院コースに乗ろうと試みたが、よくわからず、けっきょく山手へ下りてきた。おろらく10キロ弱の歩きだったのでは。なのに、なぜだか、帰りはぐったり。
(5/14)

弘法大師の霊場で山伏の修行場だったそうで、山頂には祠が祀られ、登り口の都高院だけでなく登路にも多数の石仏を見ることができる。山頂の少し東にある男岩・女岩の上に立つと耳納連山も見える。滝あり岩ありとバラエティーにとんだ楽しい山でした。
(5/13)
雨が上がりました。久しぶりの雨で、畑の野菜や庭の草木は喜んだでしょう。
白い花がいっぱい散っているので見上げると、ありました、なんだろう。こんどは見慣れない釣り鐘型のでかい花がひとつふたつと落ちている、見上げてもそれらしきものが見当たらない。少し歩いて振り返ると、あった、ずいぶんと高いところに咲いている。なんだろう。それから、ゲンノショウコみたいな花、なんだろう。
(5/11)




名前がおもしろいな〜と、気になっていました。大南林道から30分ほどで尾根にあがります。ふつう稜線は傾斜が緩やかで気持ちのいい歩きが多いのですが、今回はそうは問屋が卸さない。幾つもの小ピークをアップダウン、それがまた急で、岩をよじ上らなければなりません。しかし、シャクナゲ、ミツバツツジ、ムシカリ、ミヤマシキミが次々に現れて励ましてくれます。近くに英彦山も見えます。そして、やっと三角点。あ〜おなか空いた。
(5/5/水)

モデルがいると

わかりやすい

ミヤマシキミ

ムシカリ

ムシカリ

ミツバツツジ
紅葉の頃はもちろん素敵ですが、若葉の季節もいいですよ。みずみずしい緑がしみます。まるでオキシドール。
(5/4/火)





その姿と色、不思議な花です。竜の目を覗いてみたことありますか。何とも言えず神秘的です。
気持ちよさそうに流れている高良川でした。
(5/2/日)





世間の喧噪を尻目に登ってきました。人ひとり出合いませんでした(あたりまえか)。階段の道が整備されていると、書いてありましたが、最初から最後まで階段というのにはちょっと辟易です。ほとんどがウラジロなどのシダの道です。
黄砂が来ているようで、次第に霞んできました。おかげで見えるはずの大村湾もさっぱり。>
(4/30/金)

ぼんやり御船山

黒髪山系が一望

鏡型の石碑

有田市街

バス停
登りはじめるとまもなくアケボノツツジの淡いピンクいろの花が見えてきます。でも、蕾が多い。ちょっとはやすぎたかな。登山口に戻り、少し移動して、今度は二上山展望所へ行ってみると、こちらはピーク! あちこちから感嘆の声が聞こえてきます。いつもとは反対向きの阿蘇五岳もけっこう近くに見えます(画像4)。
やっと気温も上がって暖かくなりましたが、すぐに暑くなるのかな。夏を予感させる日差しでした。
(4/25/日)





周遊コースで、7時間の歩きでした。「九重3大急登のふたつを歩きます」と言うだけあって、稲星越までは両手を使って這うようにしての登りが続く。そして、白口岳から鉾立峠まではあのいやらしい急坂を下ります。
天気が心配されましたが、なんと、上に行くほど青空が広がり、眼下には雲海。なるほど。しかし、帰りは当然はその雲の下に入るわけで、案の定、何度かぱらっときましたが、なんとかもってくれました。
そして、JR久留米からは雨の中、チャリを漕いで帰ってきました。
ネコノメソウは始めて見ましたが、かわいいですね。
4/21/水

本山登山道

片ヶ池

由布岳のあたま

ツクシショウジョウバカマ

シロハナネコノメソウ

ジロボウエンゴサク
えっ、もう! でした。しかも、いつもの大通りのところに行く前でした。登り始めてまもなく、いきなりで、びっくり。小さな動物みたいでかわいいですね。今年は豊作?みたいです。 天ぷらにしたら美味そうだと言ったやつがいたけど、今夜のおかずにどう? ちいさなちいさなハルリンドウ、うっかりしていると気づきません。キランソウ(別名ジゴクノカマノフタ)もあちこちで見かけます。
(4/18/日)




やっと晴れて気温も少し上がりました。今年もオキナグサを見に行きました。基山の登山口である水門跡までの距離は20キロもないのですが、けっこう登ったところにあって、最後の方はチャリを押して歩きます。
オキナグサ、基山に咲いていることを知っている人がいつの間にか結構多くなってしまいました。貴重な花(絶滅危惧種)なのでので、あまり知られると、ちょっと心配です。車でも行けるし。
スミレはどこででも見かける花ですが、めちゃくちゃ種類が多いそうです。確かによく見ると、葉の形、花の大きさや色が様々です。
(4/16/金)









そんなはずないでしょ。チャリでは無理です。鳥栖あたりでいつも見かけて気になっているのですが。そのうちに食べてみたい。
トレイルの低山企画です。桜は終わっているし、紅葉の季節でもないし、時期が悪い。スミレはチャリで帰る途中、コンクリートの法面に咲いているのを見つけました。そして、ハプニング: 北茂安の西鉄ストアに立ち寄って、さあ帰ろうと漕ぎだしたら、ゴトゴトゴト・・・パンク!
冬に逆戻りしています。
(4/14)

アリアケスミレ
(4/6/火)





どういうわけか、3月29(月)、30(火)と2日続けて登ることになりました。この山、思い入れのある山です。29日(月)は都府楼跡から登り、高橋紹運の墓、岩屋城跡、馬攻め、鏡池、礎石群、焼米ヶ原へ。それから水瓶山経由で太宰府の方へ降りて行きました。
30日(火)は、政庁跡の桜並木を過ぎると日当たりのいい畑の中の道に出たあと、左に折れる道(レッツハイクで歩いたルート)をとりました。毘沙門堂の手前の方で、紅葉谷へ下りて、こどもの国(広々として、ゆっくりとお昼を食べるのにいいですね)を通って礎石群、焼米ヶ原へ。帰りは岩屋城跡経由で降りました。
今回、大原山には行きませんでした。それにしても四王寺に2日続けて行くことになるなんて、しかもその日にもう一つ・・・すごい偶然? それともよくあること?。
5番目の画像の上の方に見える開けたところが岩屋城跡、その下の桜の樹があるところが高橋紹運の墓、そして手前の大きな木のあたりは?
最後の画像は僕の好きなムラサキサギゴケです。政庁跡の桜並木の道が終わるあたりで見つけました。
それから3番目は岩屋城跡から高橋紹運の墓を見下ろしたものです。
PS: じつは、次の日31日も、都府楼に行くことになりました。桜は満開。少し散り始めておりこれ以上はないタイミング。しかも、その日の午後には天気が崩れ始めて雨。明くる日も雨だから。きっとずいぶん散ってしまうことでしょう。ちょっと寂しいですね。でも、またきっと咲いてくれるから、大丈夫。
(3/29/月) (3/30/火) (3/31/水)






足立公園の奥にある妙見神社が登山口。尾根までは容赦のない登りが続く。尾根に出ると砲台山分岐。砲台山までは片道3分で往復できる。分岐から20〜30分ほどで足立山山頂(ちなみに地図にある妙見山には登っていません)。
そこから防火帯に沿った木立の中をアップダウンを繰り返し50分ほどで沼分岐に着く。足立山、小文字山などが見える。ベンチもあり昼食。さらにアップダウンを繰り返し55分で広々とした大台ケ原に到着。そこから登り返すこと20分で戸ノ上山山頂。矢筈岳・風師山が近くに見える。
急な斜面を下り40分で住宅街に出る。オマケは門司駅まで30分の歩きでした。
ところで、山を下りるといきなり「はいはい老人」に出くわしました!おばあさんが坂道を這っていました。
(3/22/月)








この季節、桜だらけ。わざわざ人が集まるところに行かずとも、どこででも見られます。むしろ通りすがりに見事な桜を見かけることもあります。もしかした、らみんな人が集まるところに行きたいのかな、それともシートを広げ飲み食いすることが目的なのかな。
3/17/水, 3/26/金






(3/16/火)


黒髪山系については「最強の低山」とか「低山の宝石箱」言う人がいるそうな。しかし納得できる表現です。行ってみればわかります。岩場や鎖・ロープあり、展望よし、植物も豊富、とにかく変化にとんで飽きることなく、深山の雰囲気があり、とても500m前後の山々とは思えません。
今回は英山(はなぶさやま)・前黒髪(本城岳)が目的でしたが、すぐそばを通ることだし、ちょっとピストンで黒髪にも寄ってきました。これで3度目ですが、すべて違うルートです。
年木谷登山口から登り、英山、本城岳、黒髪山、そして白川登山道入口へ下りてきて、車道を一時間ほど歩いてスタート地点へ戻ってきました。
5時間ほどの歩きでした。気温も上がって(21℃)、久々に汗をしっかりかき、冬の終わりを実感しました。
(3/14/日)










たぶん3、4年ぶりの砥上岳。
「春近し」から一転、大一級の寒波で雪の予報で、夜は雨の音がしていましたが、行きました。正解でした。朝、平地は雪はありませんでしたが、途中、麓まで雪の積もった九千部が見え綺麗でした。
砥上神社からスタート。登りは樹林帯の中。冬型特有の雪が降ったり、晴れ間が出たりの繰り返し。しかし、山頂に着く頃タイミングよくちょうど雲が切れ、青空が顔を出して夜須・甘木方面や基山・九千部方面が見渡せました。そのあとは雪が降り出し、ずっと吹雪いていました。ラッキー!でした。
(3/10/水)

ラッキー!

筑紫野方面

山頂の石祠

大山祗神社の吽形

阿形

さやん神
(3/8/月)


暖かい日が続いています。2月の終わり、うちの水仙もつぎつぎに咲いて、サクランボはもう既に盛りを過ぎています。四王寺にはまだ梅が咲いていました。(2/28/日)
例年より早く来た長い菜種梅雨の貴重な晴れ間にそれっとばかり、出かけると、そろそろかなと思っていたミツバツツジはつぼみ、いっぽう馬酔木はもう咲き始めています。
ところで、いつからペリカンが真っ白に?




梅があちこちで咲き始めています。ふもとに臥竜梅で有名な普光寺がある三池山に登ってきました。三分咲き、と駐車場のおじちゃんが言ったけど、う〜ん、臥竜梅はせいぜい二分でしょう。でもほかの梅は八分とはいかずとも六分、七分ほどで、これくらいのほうが蕾も一緒に楽しめて見ごろと言えるのではないでしょうか。
で、肝心の山ですが、まあなんと言うこともなく、ちゃちゃっと登ってしまいます。でもそこそこ急なので、これが梅雨の晴れ間どきなんかだとそうはいかない(じつは経験あり)。長い石段をふたつ登ると伝説の三ツ池がある三池宮に到着。ヤブツバキの群生する中、縦走路のアップダウンのあとまもなく頂上。山頂のとなりは広い草原になっていて眺望がすばらし。曇りでしたが、とりあえず三池港のむこうに雲仙のすがたもかろうじて確認できました。帰りは三池宮を通らず、一気に普光寺まで下りてきました。
(2/16/火)

ちょうど

見ごろ

子を抱く狛犬

ヤブツバキ

雲仙
霧氷がお目当てでしたが、ごらんのような状態。朝の冷え込みはきつくて、下はガチガチで歩くとジャリジャリ。天気予報の傘マークはいつの間にか消えて、素晴らしい天気。今年のトレール山の会は滑り出し好調。怖いくらいです。
御嶽権現社から登り、鶴見岳の西側を回り込み、馬の背に乗る。気持ちのいい尾根歩きを楽しみながら、鞍ヶ戸I峰、II峰、III峰へと進む。間近に由布岳の威容が臨める。となりに倉木山、そのむこうに久住連山が横たわっている。先日登った内山・伽藍岳はすぐそばだ。縦走もできる。馬ノ背まで戻り、今度は鶴見岳山頂をめざす。別府湾が真下に広がる。国東半島のギザギザになった山々が見える。
ところで阿吽のおふたりは髪型が違いますね〜。
(2/7/日)

阿形

吽形

由布岳と久住

内山・伽藍岳

鞍ヶ戸

馬の背

水墨画

別府湾

国東半島

由布岳
高良山を案内しました。
(2/2/火)
観測史上初の暖かさを記録した先週の「大寒」の影響で、雪は無し。お目当ての「完全凍結の御池上を歩きます」もごらんのとおり。
しかし、恐ろしいほどの空気の透明度!さすがのリーダーも、こんなの始めてだと言ってたほどの眺望。阿蘇五岳、由布岳、英彦山はもちろん、なんと霧島、普賢岳、石鎚山(愛媛)まで!
(1/24/日)

寝観音

真っ青!

石鎚山

御池

三俣山と由布岳

英彦山

中岳山頂と由布岳

彼方に霧島

普賢岳

坊ガツルと由布岳

仰ぎ見れば

空には月
天気がよくて、風がなく、雪が多くて、という最高の条件でした。雪の白さと、空の青さがまぶしかった。みんな、はしゃぎまくりでした。今回は、言葉よりも画像に語ってもらいましょう。
(1/17/日)

ぼく、さむい

帽子

つらら

鹿の親子

足跡

ふわふわ


由布岳の頭

出発しま〜す

こけた!

満開!

中岳・上宮

氷柱

スキー場
怖そうなのとか、微笑ましいものとか、かわいいのとか、じつに多種多様(あたありまえか)。神社に行く時は狛犬を見るのが楽しみです。これは千栗神社の狛犬です。馬がいました。なんで?
ところで、焼ガキ、おいしいですね。大好きです。じつは、岡山県産が大きくておいしいみたいですよ。
1/16/土





この冬一番の寒波だそうです。そういえば、むかしはよく降ってました。小学生のころ2月いっぱい雪消えなかったことがあったような記憶があるのですが。そういえば雪の日、中学のとき、友達4、5人と授業をさぼって篠山城まで遊びに行ったことがあったな〜。
(1/13水)

とはいっても、今回もやはり山頂には行かず、後谷の登り口の左側から竹の子コースへ行く道を登り始めました。車道に出て少し戻ったところに登り口があるのに以前から気がついていたのですが、どうも途中で途切れて引き返すがヤブコギしそうな気がしてやめていたのを今回挑戦。意外と急な登り。そして、なんと、奥の院の鳥居のところに出た。車道までの道もけっこう急だし、高良山の数あるコースの中では一番きついところかも。
というわけで、自分の庭のように知り尽くしていると自負していた高良山にもまだ僕の知らないところがあったということでした。
(1/7木)
今年初の山です(2日に高良大社には行きましたが。ちなみに高良山の頂上は森林公園のところです)。天気予報に雪マークが付いていたので、どうせ家にいても寒いし、山にでも行った方が暖まる、ということで行ってきました。
宮地嶽神社の鳥居から登って10分ほどであっという間に山頂。宮地嶽神社の祠があります。やはりちょっと吹雪いてきました。綿菓子をちぎったようなふんわりとした雪ではなく、細かい氷の粒のような雪。でもそんなに続きはしませんでした。
今回は縦走。奥山(312m,こちらの方が高い)を経て、河内ダムの方へ下り、ダムを一回りしてスタート地点に戻ってきました。
頂上は気持ちのいい草原で、見晴らしもよく、気候のいい時期にはピクニックにいいのでは。
参考のため地図を載せました、が、なんと杓子ヶ峰は載ってない。ひどっ!
(1/5水)

スタート

宮地嶽神社

さむそう!

地図です