�@�������炦�����āA��J�ցB


�@�l��Ƃ́A���A�a���A�V���A���̂��Ƃ������ł��B�u�ӂ���̓������v�u�ڂ��܂�����A��낵�����肢���܂��v�ɑ����Đ������A�V�����ɂ��Ďv�������炵�܂��B���x�͎��Ƃ̌����������ɂ��ďƏ������킹���܂��B��Ƃ��ē����͂Ȃ��B�Ŏ����̂ɉ����ł��邩�H�����炭�u���Y�����Ɓv�ł͂Ȃ����B���̂悤�Ȑl�����ɊŎ���Ă��炦�邱�Ƃ͍K�^�Ȃ��ƁB������x�����t�����A�ނ�Ɏ�����킹�����Ȃ�܂��B
�@�A��čs���Ă�����Ă܂����B���N�Ɠ��������o�[�B���N�������܂����B



�@���͐���ȖY�N��B�H�����H�����A�ݑ܂��j��邩�ƁA���Ƒ傰�����ȁB�V�C�͂������A�����Ȃ������˂Ă��傢�ƍs���Ă��܂��B�l�������B�R�N����������ɋv���Ԃ�ɉ�܂����B�P�Q���������Ƃ����̂ɂ܂����ꂢ�Ɏc���Ă���Ƃ��낪����܂��B���ʎQ�����オ���Ђɂ��Q�肵��ʂ�����ĉ��{�ցB�Ȃɂ�炠���Ă܂����B�l�I�Ɉ˗����ꂽ���̂炵���̂ł����A�ʎ�S�o�������z���L�������āB�R���������Č����R�ցB�Ҋ��r��̍g�t����������������A��܂����B








�@���c�n�̓o�R������s���܂��B�r���Ŕ����ɏオ�肿����Ƃ����ߓ��ł��B���͔�����쑤�ɏ������肽�Ƃ���ɂ���܂��B�Q�U�O����Q�X�Om�ʂ̂Ƃ���ł��B�������w�ǎU���Ă��܂��Ă��܂��B�܂����N�B�A��͂���ɋߓ������Ē��ڒJ�։���čs���܂����B

�@�������ꂪ���@�B�����{�ɔN���̈��A�����Č����R(259.2m)�ɂ���āA�^���[���ɏオ��܂����B�܂��c���Ă܂�����B�Ҋ��r��̂��݂��B�h�E�_�����܂�����܂��B�����͓�ʁA�A��͗ѓ����B�r���A�����̂��ߒʍs�~�߂Ƃ��邪�s���Ă݂�B���炭�s���������낻��Ǝv�����Ăђʍs�~�߂̕W���A�u���b�N����Ă���B�Ђƈ�l���炢�ʂ�邾�낤�B����Â������B���S�ɕ����B�����Ԃ��Ē|�̎q���[�g���ŒZ�ʼn���A�����{�܂Ŏԓ���߂�B���̂��ƃ^���[���̂P�R�K�܂ŏオ��܂����B�W���͂U�Om�قǁB





�@���F�a�@���X�^�[�g�B�����̂悤�ɍ@���Y���オ��܂��B���̃��[�g��������C���������ł��ˁB���邢���R�т̔��������B�_�͑����ł������˂�������܂��B���������[�g�ɍ������A�S�S�S�s�[�N���o�āA�����ȃs�[�N������߂��āA��{���痈�����Əo�����A�����ɎR���B�A��͍Ō�܂œ��������[�g������܂��B�������҂��Ă܂��A�ӂӂӁB
�@�A��r���Ȃ̂ŁA�����R�̋�ǔ��֓���������s���Ă݂悤�Ǝv�������܂����������Ă��܂��Ď��Ԑ�A�����s���ł����B�c�O�B

���Ȃ��G�R����

���Ǖ���

�������ɂ̂�

�召��W��

�T�U���J��

���ꂢ�ł�

�����Ȃ���

�~�C���A�~�^�P

������

�Ȃ��Ȃ�

������
�@�Y�ď����R�[�X�̓�������X�^�[�g���r������ڑ����[�g�ɓ���܂��B�X�Y���o�`�̑�������̂ʼnI�[�g���ł��Ă��܂����s����Ƃ���܂ōs���Ă݂悤�Ǝv���܂��B�����Ȃ�A�[�R�̔����ɏオ�������̂悤�ȂƂ���ɏo�܂��B����ɐi�����Ƃ���Ƒ����Ɉ�C�n�`�����ꂽ�̂ł���ĂĈ����Ԃ��I�[�g�ցB�܂��Ȃ���R�[�X�ɍ����ł��B�c���H����L�тĂ�������ɏオ�肢�悢��C�`���E���T���B���ꂩ�ȁH���ꂩ�ȁH�ƍs�����藈���肵�ĕ�����������킩��Ȃ��B�����Ɖ����ׂ����Ēn�}�������čs���Ă����悩�����B�w�K���Ȃ��ȁB���傤���Ȃ����߂ė\�肵�Ă��Ȃ����������R�֏オ���ĒY�ď����R�[�X������Ă��悤�B����ɂ�����R���ɒN�����Đu���킩�邩���m��Ȃ��B�s���|�[���I�H�����̃I���W���ЂƂ�B��J���ċ����Ă���܂����B�Ȃ�ƎR���t�߂���쐼�ɐL�тĂ�������̐�ł����B�������������r���܂ł͍s���Ă��̂ł����ˁB�P���Ԉȏ�̃��X�����Ă悤�₭�H�蒅���܂����B���܂��ɂ����قڏI����Ă��邾�낤�Ǝv���Ă�����Ƃ�ł��Ȃ��A�܂����������ł��B

�悢�������

���ǎR

�w�U����畔���

���

�����R

����͎R������

���̕���

��������

�����

�܂�

�����ł�
�@��͂�x�������悤�ł����A��畔�ƐΒJ�̏c���H�͂���ł��C���������ł��B��������A�r���A�͓��_���̏�����A�W�����I��邠����̐_�Ђ̍g�t�������ł����B�v��ʎ��n�ł��B












�@��N���̌��J���I��������A�s���Ă��܂����B�h�E�_���c�c�W�͂܂��ł��������Ƃ͕���Ȃ��B�ɓ����p����̐Ί_���V�����Ȃ��Ă��܂����B���ꂽ�̂ł��傤���H










�@���悢���R�����ĕ��n�ւƍg�t������Ă��܂����B���Ǒ�Ђ֍s���Ęh�m���x�o�R�ʼn���Ă��܂����B���O�̂��Q��ɂ͎����Ă����̉��₩�ȓ��B







�@��������}�[�m��܂łT�O�Om�قǂ������ł��B�����ɓn���Ă������o���čs���܂��B��̉��Ƒ��̕���B����ɍs���܂��B��̓��ɏo�đ�������B�����͂��܂肠��܂���B�n���܂��B����������ƌ����炵�̂����Ƃ���ɏo�����ȋC�z�B���q�n�Ȃ̂œ��͂����炱����ɂ���܂��B�������u�ɏo�܂����B�Ȃ�Ƃ����h�炵�����₩�ȋu�˂��L�����Ă��܂��B�����イ�̎R�X�����ꂢ�Ɍ����܂��B�����͒J���u�ł��ˁB�}�[�m�̋u�Ɩ��t���邱�Ƃɂ��܂��B���āA�̂ǂ��Ȍ��i�����Ƃɂ��đ�����ɍs���܂��B����čs���Ƃ��傤�ǂ܂���PR�����B�e�̏��������Ă���Ƃ���ł����B���炭�������܂��B�Ȃ�Ƒ�s��������݂�悤�ł��B����J���܂ł��B�����Ⴂ���Ȃ��A���ǖʔ������̂������Ă��������܂����B
�@���͂����B�r���A�������ɂ������u�����イ�E�킢���̓W�]�����v�̓W�]��֏オ��A�쏬���̖���O�ł����B�A��͖�o�R�ł��B������������܂イ���Q�b�g���āA����ɍL��̑����Ɋ���ăC�`���E���Ϗ܁B�����������ł����F�Â����i��ł����悤�ł��B�k�J�̍g�t�͂قڏI����Ă��܂������A���ꂢ�ɐ��ꂽ���A�[���̈���ɂȂ�܂����B






















�@���N�͏I��肪���A���Ƃ��͂ڂ��ڂ����ȁA�Ƃ������Ƃ���B


�@�o����̂�����O�̎ԓ����y������B�������z���čs���A�o�R���͂Ȃ�Ƃ�����܂���ł����B�g�t�͂܂������ƌ����Ă����قǂȂ��B�܂��܂��ߌ������čs���R���̂����܂������i�ɂ͖ڂ��ނ�Ƃ��āB����ɂ��Ă��U�̃s�[�N��i�������̏c���H�͂Ȃ��Ȃ��̂����ł��B���̔����A���̔��S�A���ȁB

��z���܂�

�߉ށE��O

���R

�Z�������E
�@���₩�ȓ��B��̂��������ĕ����Z���^�[�ցB�X���o�ē�����Ă܂����B���������āA���і݂����y�Y�ɔ����ċA��܂����B



�@������Ƃ�������܂����B����ς��R�╽�n�̍g�t�͏I�荠�������ł��ˁB�܂��ʍs�~�߂ł������A�ԓ�����J���A��������J������Ă���Ƃ��낪����܂������l�͑��v�A�Ԃ́E�E�E�A�ł��ʂ������Ƃ�����܂����B���ꂢ�ɐ���Ă��܂��B�����̎R���ʐ^�͋v���āE�������ʁB�߉ށE��O�A���R�������܂��B






�@�r�̔_���U�荞�݂ɍs���Ē����R�ɍs���č���ɁA�ƍl���Ă��܂����������R�����������B�k�����������i�̔����ȉ��P�O�L�������������ʂ��̂̃X�s�[�h�B�Ƃ��Ƃ����܁B�Ȃ�Ƃ�����ɂ͒H�蒅���܂������B�܂��܂������R�ɂ͋��ۂ���܂����B
�@�O��P�O����B�܂��ł��ˁB��͂艺�{���炢�ɂȂ�Ȃ��ƁB�����_���L�������ł��܂��B�h�����ĉ_��⑽�ǎR�n�������܂����B



�@�炢�Ă͂��܂��������܂葽���͂���܂���B�ۑ����܂łň����Ԃ�����ł������A������n���Ă��܂��܂����B�����������֍s���āB�����B�A��͔����R�[�X���B����ς肫���R�ł��ˁB

����Ƃ���������

���̉�

���݂����ł���

�Ε�

�ۑ����̎�O

�}�㕽��

�q���W���I��

�����i

�p�F�R����
�@������Ƒ������邩�Ǝv���܂������A����t�߂͂��łɉ߂��Ă���A�o�[�h���C���͂܂��܂��B���ԏꂠ����͂��������A���������傤�ǂ悢���ł͂Ȃ������ł��傤���B�\��ƈ���Ĉ���܂�Ȃ͎̂c�O�ł������A�܂��A�悵�ƁB

�{���̉�

�g�t�̃T���v���H

�����

��ї���

�p�x���

�o�[�h���C���t��

�Ώ�

���[����

������Ԃ̐�

�o�[�h���C������

���Z�_��
�@���傤�͌Ñm�s�R�i�R�\�d�T���A�R�\�a���}���j�ɍs���Ă݂悤�Ǝv���܂��B���܂�l���s�����r��Ă���悤�ł����B��ϓ��̎l���ɂ������������l���A����͉i�����̂��Ƃ�낤�ƌ����Ă܂����B���͂�����Ƃ������Ƃł��B������݂����肪��������ꂵ�ďo���B�ԓ���H���čs���܂��B������Ɖ��܂����Ƃ���ɂЂ�����ƘȂ�ł��܂��B���̍����������Ƃ��Ă��܂��B����ł��傤�B���̗��ɂ���炵���i�X���B���`��s���Ƃ����B�i�X�͂�����ƂŏI���܂������������Ȃ̂ŋ����ɍs���܂��B��͕揊�̂悤�ł��B
�@���A�A��܂��B���Ƃ͂������B���̑O�̎ԓ��։���Ă��̂��ƕ�����E�B�b���s���܂����ǂ��������Ⴄ�悤�ȁB����ɖ߂�A����ł������Ǝv�����߂Đi�݂܂����A����ς肨�������B������x�����Ԃ��܂��B�Ԉ���Ă܂����B����������̂ł��B�ЂƂڂ͍��ցA��ڂ͉E�ցB��ڂʼnE�֍s���Ă��̂ł��B�����B��ϓ��Ŏ��{���̂������ōs���|��ɂȂ炸�ɂ��݂܂����B






�@�i���o���M�Z��������悤�Ȃ̂ōs���܂����B���r�̗�����オ��܂����B���̂������̓R���N���[�g�ܑ��B�������͂�}�◎���t�₪�ς����ĕ����ɂ����B�Q�O���قǂő����ցB���`��A���Ȃ��ȁ[�B���������Ȃ̂ʼn��R�܂ő���L���܂��B�b������ƉE��Ƀs�[�N�炵�����́B������������Ċ�����������Ă��邩���B��͂�A�����ɏo�����炵���ӏ����B����������֍s���ċA��ɏオ�邱�Ƃɂ��܂��B�͓��_���ւ̕���炵���Ƃ��������ɏ����i��ł݂܂��B���͑����Ă���悤�ł����r��Ă���B�����Ԃ��ĉ��R�֏オ�������ƁA�������Ƃ̍����n�_���m�F�B����ጩ���Ƃ������B






�@�v���Ԃ�ł����B���ׂĂ݂�ƂS���Q�Q���ȗ��A���傤�ǔ��N�Ԃ�B

�}���U�炩���Ă���

�E���N�T
�@������Ǝv���s���Ă͌�������ǁA�J�j�m�c���A���N�͐h�����ĂQ�A�R�A���N�́A����ς茩������܂���B�s���͂������������ōÂ�������Ă܂��B�A��A�r���̃X�[�p�[�Ńq�V���܂����B�n������Ȃ��Ƃ���܂���ˁB���������������Ă����Ăւ���܂����B
�@�ߌ�͕����ĕ����Z���^�[�ցB





�@�����̉��ɒʍs�~�߂̎D������܂��B�r������I��H���ł��Ă���̂ōs���Ă݂܂��B�A��͖{��������܂����B���N�Ɠ�����Ԃł����B���N�̉J�̔�Q�ł͂Ȃ��悤�ł��B�Ƃɂ����T�C���E�V���W���������B�V���W�����炯�B����Ƀ��}�n�b�J�B�P�R�Om�܂Ŏ��]�Ԃŏオ��̂������B






�@���ʎQ���𒓎ԏ�܂ŏオ��Ɖ�����̐Βi�̓o����ɁA�|�����̂��ߋ����ւ͍s���Ȃ��A�Ƃ���܂��B���{�ւ͍s����Ƃ������ƂȂ̂ŐΒi���オ�������Ƃ́A��ʁA���m�@�A������x�A���X�A�����Ė߂�͔���������k�����狫���ցB���傤�ǂ����B���܂����i�ł����𗎂��������A�|�����̌ߌ�̕���������Ƃ������ĉ���Ă��܂����B





�@����ő��������Ă����l�Ɉ��A�����Č��t�����킵�Ă��邤���Ԃ̏�����Ă��܂����B�����Ղɍ炢�Ă����Z���u���͊��������č��z�Ŏ�������̂ō������������Ă��܂����Ƃ��A�L�����v�ꂠ�Ƃ̎l���t�߂ɃZ���u����L�b�R�E�n�O�}������Ƃ��B�͂��A�m���ɂ���܂����B�q�Q�ɂȂ����Z���{��������������������܂��B
�@���āA������Ɗ�蓹�ł��B�u���Ԃ�̑���ʂցv�P�R�Om�قlj���܂��B�Г��R�O���ʂōs����ł��傤�B�^�J�N�}�q�L�I�R�V�̌Q���������邽�߂ł��B�������~�J�G���\�E�����������͂��B�������ɑ�J�̉e�������肿����ƍr��C���ł������҂ǂ���ł��B�A�P�{�m�\�E�������B�������Ĉ����グ�܂��B�Ƃ���ŁA�J�����̌Q���̓^�J�N�}�q�L�I�R�V�A�ԓ��̘e�ɂ������̂̓q�L�I�R�V�Ɣ������܂����B



























�@���̊Ԃɂ���������H�̋�C�ɂȂ�܂����B�v���Ԃ�ɒ����R�s�����ƂɁB���ԏꂩ������n�߂�Əォ��l������Ă��āu�ʍs�~�߂ł���B�j�������Ă����āA�l�������ς����āv���x�͉�����l������āu���݂܂���A�o��܂���A��J�̎��V�J�����炢�����J�����肵�āA���������ƌ����Ă��ł����ǁv���Ⴀ�d�����Ȃ��B���łɈ����_�ЂɊ���ċA���Ă��܂����B

��������

�g�L�n�n�[

������Ƃ���Ō��܂�

�c�O�ł���

�����_�Ђ̗�
�@�ɔV�����[�����̔����o���ɂ����܂����B��܂��܂�������܂����B�ق�̂�����Ƒ���L�����������ցB���̌G�R�̓��A�錴��̂����߂��ɂ���܂��B���������M�ɍU�߂�ꐨ������Ŏ��Q��������~���i���Ō�̓���j�̕�����邽�߂ł��B����܂����A�m���ɁA���̗��ɂЂ�����ƁB�A��r��������Ɗ�蓹�����ăL���S�W�J�̗l�q�����Ă��܂����B�����炭�����I����Ă��邩�Ǝv���Ă��܂������A�c���Ă���̂��͂��ɂ���܂����B�悩�����B

������

����~���̕�

���ꂢ�Ȃ̂�

�܂�������

�Z���_���O�T
�@����ς�܂��ł����B�A�P�{�m�\�E���Ȃ��������B��������C���ŁA�������āB�ŋ߂��C�ɓ���̓��̉w����߂ł����B�B












�@�߂��ė��܂����B���X�Łu�����̂悤�ɗ����Ă����Njߍ������Ȃ��̂łǂ����ꂽ�낤�Ǝv���Ă܂����v�ƌ����Ă��B




�@�v���Ԃ�̃V�G�}�B�`�����ōs���̂͂����Ƌv���Ԃ�B
�@NY�̃M�^�[�E�l���b�N�͔p�ނ��g���ăM�^�[������Ă���B�P�O�O�N�`�Q�O�O�N���́B���ɂ͋������ꂩ���������̂�����B�f��͍H�[�̓���ƁA�����ȃM�^���X�g�����Ƃ̉�b�≉�t�̉f�������݂ɗ����B�M�^���X�g�����͓X�œn���ꂽ�M�^�[�ʼn��t����B�M�^�[�̘b�A�~���[�W�V�����̘b�A���I�Șb�������ĉ��t����鉹�����炵���B�M�^�[��{������Ȃ̂��A�͂��߂Ď�ɂ���M�^�[������Ȃ̂��A���̐l�̃X�^�C�����ۗ����l���������Č�����悤�B
�@�G�߂͂�������Ăɋt�߂�ł������芾�������܂����B






�@�ʍs�~�߂̏���������ōs�����Ƃɂ���(640m�t��)�B��{���ԏ�܂łS�O���B�܂��̓��}�n�b�J�B�A�L�`���E�W�B��������H�̉Ԃł��B�A�L�m�L�����\�E�B�A�P�{�m�\�E�A�Q�������ł����炢�Ă��܂��B�V�C�͈ӊO�ƈ����B���ɂ��~�肻���ȋ�B�~������~��ɂȂ�P�ƃJ�b�p�̐��b�ɂȂ�܂����B�J�R�̓r���ɂ��郀���T�L�Z���u�������Ɋ�蓹���܂��B�~���R�U�T�����Ă���B��������Ə����X�����āA�ق炢���B�Ȃɂ���A�Ƃ������炢�d���Ȋ�������A���݂����Ȃ��炢�ł��B�R���ւ͍s���������Ԃ��ēV�R�ցB���ʂ̃Z���u�����U����Ă��܂��B�������ɓ��͂�����ƍr��Ă���悤�ł��B�R���ł����H�ׂĎU��B�܂��}�c���V�\�E�����ꂢ�ɍ炢�Ă��܂��B�E���o�`�\�E�͌�������܂���B�g���J�u�g�����ăR�S���O�T�����Đ܂�Ԃ��A����ς肢�Ȃ����Ȃ��Ƃ��낤�낵�Ă�ƁA�Q�������܂����B���傤�̂Ƃ���͂���ł����ق��B




































�@���܂킵���v���o�̎��R���B�Ăт����ɗ����Ƃ����낤�Ƃ́B����A�����ߋ��̂��ƁA�Y��悤�B���āA�����̓V���X���������܂��B�T�O�Om����o���B�y���A�b�v�_�E�����J��Ԃ��A���������x���グ�Ă����܂��B���̂����Ə�̕��ŕ����r���[�r���[�Ɖ��𗧂ĂĂ��܂��B���R�т̖ؗ��̒��ɂ����������Ă��܂��B�悤�₭�O�����B��畔�`�ΒJ�R�̏c���H�̓r���ł��B�W���͂V�Q�Om�قǁB���������畔�����ăV���X������T���Ȃ���i�݂܂��B���邢��B�Ƃ������V���X�����������Ȃ��B�����ȏ�s�����Ƃ���ł����ɂ������Ԃ����Ƃɂ��܂��B�ΒJ�R�ւ͊�炸�ɖ߂�܂�����������ɂ������ς������悤�ł��B�܂����x�B
�@�V���������F�����̃V���X�����͔w�������āA�t�ɂ͐^�Ƀ^�e�̗t�����͂����茩����B���炩�ɕʎ킾�낤�B�ŁA�ΒJ�E��畔�̂��V���X�����A�Ï��R�̂̓x�j�V���X�����A���R�̓A�P�{�m�V���X�����Ƃ������Ƃ��킩��܂����B�Ӂ`��Ȃ�قǁB
�@�W�̂Ȃ��ʐ^���������Ă�H���������A�����͂��܂��t���ł��B


















�@�����������܂��B���q�{���獂�Ǒ�Ђ܂ŁB�ǂ���獡���͓����I�B����������Ă܂����B�Βi�͌ߌォ��͒ʍs�~�߂ɂ���ƌ����Ă܂����B�A��ɘE�̉���ʂ�߂������h�T�b�Ɖ������Đ��Ȃ��̂��������ꂩ�痎���Ă܂����B���v�H










�X���U���i���j�F���R(967m)
�@�V�R�͑S�ʒʍs�~�߁B�ł͋��R�ցB�ԗ��̑�R�[�X��ѓ��I�_����X�^�[�g�B��ɉ����ĕ����Ă����܂��B���Ȃ�̐��ʂł��B���x�����x���n���J��Ԃ��܂��B�n��ӏ��ɋꗶ���܂��B�V���X�����͎c�O�Ȃ���܂��Q�݁B�ł����J���������܂肪����܂��B�X�Y�R�E�W���͍炢�Ă��܂��B����ł̓A�S�⓻�ł͂Ȃ����o���[�g���Ƃ�嗬���L�[�v�B���Ɍ�����ς��܂��B��������X�������Ȃ�܂��B�}�o��o�ڂ茨�ɏオ��ƎR���͂��������B����Ƃ����ł��B
�@�A��̓A�S�⓻�o�R�ʼn��R���邱�Ƃɂ��܂��B�Ō����ւ̏c���H�������s���ƃW�����N�V�����B�A�S�⓻�����܂��B���K�ȓ��ł��B�r���X�Y�R�E�W���̌Q��������܂����B�قǂȂ����H�ƍ����B�܂��n�����Ȃ���A��܂��B���[���������A�ł��y���������B�����R�ł��B

�J���~�h��

���傤�ǂ悢

痂�����

�I�I�q�i�m�E�X�c�{

�N�T�A�W�T�C

���ʂ�����

�V���X����

�X�Y�R�E�W����

�����ς�

�h�����č炢�Ă�

�����������

����������ς�

�~�J�G���\�E

�ԂƂ��

������

�����p

�_��Ƌ����R

���~�W�^�P

�܂�������

��J���܂�

�~���}�J���X�A�Q�n

�����t��
�@���傤�͓V�C�͂��܂�悭�Ȃ������ł��B�����ɋ߂Â��ɂ�J���~��o���A����Ђǂ��Ȃ�A�ł��������珬�~��B�U�Ă��邤���Ɏ~�݂܂����Ƃ��B

�~�c�K�V��

�T���M�L���E

�~�Y�g���{

�T���M�L���E

�k�}�g���m�I

�I�g�R�G�V

�R�o�M�{�E�V

�i���o���M�Z��

�c�������h�E

�}�}�R�i

�c�`�A�P�r

�c���t�l�\�E

�i���e���n�M

�l�R�n�M

�������R�E

�R�E�]���i
�@�J����i���B�܂��Ԃɍ����ł��傤�B�܂��r�����B�L�b�R�E�n�O�}���������B�L�o�i�A�L�M���͂ڂ��ڂ��炫�n�߂Ă���B�~���}�E�Y���͂�����ƒr�̎�O�ɂ���܂����B�r�����܂��B�L���~�Y�q�L�A���}�z�g�g�M�X�A���m�l�O�T�A�C�k�C�g�q�Q�A�R�P�I�g�M���A�g�t�������E�Z���S�P�Ȃǂ��y���߂܂��B�����R�i����j�Ɋ���āA���x�͂W�X�V�s�[�N�̕��֍s���܂��B�����͎R���̊��������������̂ł���𗘗p�B�������āA����ɐi�݃p�m���}�W�]�╪����߂���B�~�J�G���\�E�͂܂��Q�݁B�b���s���ƁA���܂����B�i�c�G�r�l�B�������������ł��ˁB����ō����̔C���͖��������B�߂�܂��B�A��͎R���o�R�ŁB�������������A�L�m�M�������E�\�E�����������ɁB


















�@���֏�Ɋ���Ă݂܂����B���ǂ낭�ق��ґ�ɍL���~�n�ŁA�傫�Ȗ��T���Ɩ��Ă���B����ȂƂ���Ƃ͒m��Ȃ������B�ǂ���痤�R��n�̐Ւn�̂悤�ł��B
�@���͒���������Ă����̂ł����ߌ�ɂ͉J���~��o���܂����B����Ȕ��ł́B���̂������̂ł����B

����

���쓃

���R��

�h�C�c���ؗ��ԗ��

������

�~�`��O�u��

����
�@�~�J�����܂��B�C���͒�߂Ȃ̂ł��������뎼�x�������B�~�J�̍��ԁi�H�j�ɂ�����ƍ��ǎR�ցB���ʎQ������オ���č��Ǒ�Ђɂ��Q�肵�ĉ���͋g���x�Ɋ��܂��B���̎����ɂ����ɗ���̂͏��߂āH�đ�����Ȃ����͋C���Ⴂ�܂��B�����r�̉��ɂ��Ă��ȉƂ��ł��Ă܂����B






�@�䕗�̂�������B�C����������܂����B�R�Q���I���q�{����Õ�a�R�[�X�A�k�ʁA�R���A�����A���Ǒ�ЁA���q�{�B�Ԃ͂���܂���B���u�~���E�K�ƃ~�Y�q�L���炢�B�c�N�b�V�������悤�ɂȂ�܂����B����ς�A������x�R���͗������ł��B

�@��^�̑䕗�P�O�����������߂Â��Ă��܂��B�����̒��ɂ͎l���ɏ㗤�B�����͂܂����ꂢ�ɐ���Ă��܂��B�ߌ�����������炿����ƉJ���~�邩���H
�@�V�R���ԏꂩ��B�܂��̓A�L�m�^�����\�E�A�L���~�Y�q�L�A���ꂩ��V�M���J���}�c�A�Ԃ͂܂��܂��̃A�P�{�m�\�E�B�b������ƃV�����\�E��T�C���E�V���W���A�z�g�g�M�X�ƁA���Ȃ��݂̉ԁX������܂��B�I��肪���ł����I�J�g���m�I�������ς��ł��B�R���ɏオ��Ƃ����Ȃ蕗�������B���͌��������ɂȂт��āA�}�c���V�\�E�������Ƃ��Ă���܂���B�V�C�͂܂����������Ȃ̂ŁA�����H�ׂāA�V�쒓�ԏ�̕��։���A�ԓ�������ēV�R���ԏ�֖߂邱�Ƃɂ��܂��B�P�O���������ƁA����܂����A���ړ��Ẵ^�}�A�W�T�C�B���܂��͂����č炢�Ă������̉Ԃ̑S�e�����߂Ėڂɂ��邱�Ƃ��ł��܂����B�����ł��ˁB

�A�L�m�^�����\�E

�V�M���J���}�c

�L���~�Y�q�L

�V�����\�E

�T�C���E�V���W��

���}�z�g�g�M�X

�ċ�����

�m�C�o��

��Ղ̈ꖇ�H

�q���A�U�~

�I�~�i�G�V

�H���R�̓d�g��

�܂��c���Ă���

�g�E�o�i

�m���E�c�M

�������I

����ȃ^�}�S��

�ўւ̂悤��

�����

���X��

�J����

�܂�ʼnԉ�

�s�v�c�ȉԂł�

�I�J�g���m�I

�W�C�\�u�̃^�}�S

�傫�Ȋ��ł�

�������Ȃ��H

�i�c�A�J�l
�@�R�V�����̏������������܂��B���N�قǂł͂Ȃ��Ƃ͌����Ă��˂��B


�@�V�l�̓m�L�����v�ꂩ��B�Ђ���������̋}�o�ł��B���R�ւ̕���͊���悶�o��܂��B�����ɃM���o�C�\�E������܂��B���ꂩ��V���X�������B�قǂȂ����m�@�B������Ɨ��݂܂��A�叫�B�����o�āA�R���B�N�����Ȃ��B������Ƒ��������ɂ��܂��B���̂����c�̂������̂ł��������ƈ����グ�܂��B�L�c�l�m�J�~�\���̎p�͂܂����������܂���B����Ȃɂ������̂ɁB�����Ȃ�ƎR���ɂ����������͋M�d�ł����B�A��ɃJ���K�l�\�E�����ɍs���܂������A���ԏ�̐�̎ԓ��e�̂����炢�Ă��܂����B


















�@�����͉ĉz���P���B���̗ւ���������Ă��܂����B�Βi�͂��ꂢ�ɕ�C������Ă��܂����B��[���������̂��т��q���m���������������ďo�ԑ҂��B





�@�����x������o��܂��B����ѓ��̏I�_�܂łܑ͕����ꂽ���B�n�O���\�E�A�_�C�R���\�E�A���u�~���E�K�������ς��B�A�P�r����Ȃ�B�I�_����͎R���B�J���~���Ă��ĎP���o���܂������債�����Ƃ͂���܂���B�q�i�m�E�X�c�{�͂����I��肪���B�w�ǎ�ɂȂ��Ă��܂��B�R���܂ł��ƂS�O�Om�ʂ���I�I�L�c�l�m�J�~�\���̌Q�����n�܂�܂��B�Q�������ł����قڌ����ł��ˁB�R���߂����Q�D���ł����B�Ƃ肠�����R���ւƏオ���Ă����ƁA����I�T���R�^�P���A����ɂ��́I�т����肵���B������Ƃ����̂����H�ׂĂ���W�]��ɂ��s���Ƃ��܂��B�A���e�i�̎���̓E�o�����A�R�I�j�����������B���R���܂��B�J���~���Ă����̂ŋ}���Ŏ��ёт̒��֓���܂��B���������A�����x���ɂ����l���Ȃ��Ȃ��オ���Ă��Ȃ��Ǝv���Ă�����R���Ɍ���āA�u�y���~��̉J�ɂȂ����̂ŎԂŏオ���ė����v�Ƃ������Ƃł����B���肪�������Ƃɖl�����͖w�lje�������ɂ��݂܂����B����ɂ��Ă����̏�Ȃ����������ł����B
















����Ă��܂�

���T�V�A�u�~������

���u�~���E�K

���q�r

�ċ�
�@�C�ɂȂ��āB�����A�~�J�����錾�B��C�̏�Ԃ��܂��s����łǂ����ȂƎv���Ă�������ǁB��������C���͏オ���Ă��܂����B�g���{�\�E�́A�I����Ă��܂����C�`���N�\�E�ɍ������Ēr�̟���Ǘ����̌���ɍ炢�Ă��܂��B�������낢�`�ł��B�܂�ŋ����B�E���K�T�\�E�͎�ɂȂ��Ă��܂��B�L�m�R����������o�Ă��܂��B�L�C�{�J�T�^�P���W�c�ŁB�����t�߂ɃE�c�{�O�T���܂�����܂����B����ɂ̓I�g�M���\�E���B�L����͓��A�Ŏ������B












�@�m���ȏ��ɂ��ƍ炢�Ă���Ƃ����B�Ȃ�قǁA�Q������܂�������炢�Ă��܂��B�i�c�Y�C�Z�����^������B�q�I�E�M���炢�Ă��܂��B���������A�����r���A�������������Ă����ɍ���̓����ɂ��q�I�E�M�����܂����B���Ǒ�Ђ܂ōs�����Ƃɂ��܂��B���C�������B�����������������B�E�X�L�k�K�T�^�P�͎c�[������ƁA�^�}�S��������m�F���܂����B
�@�����~��Ȃ����Ǝv�����璋�߂��J���B��U�͎��܂�܂������A�}��������ł܂��������Ȃ�A�J�h��B�܂��Ԕ�������ō~��o���A������x�J�h�肵�ċA���Ă��܂����B








�@�U���Q���ɂU�K����P�U�K�Ɉڂ�A�V���P�P���ɋv���ă��n�r���ɓ]�@�B��������A�ʉ�ɍs���r��������Ƃ�����蓹���ăR�I�j���������ɁB������ɍ炢�Ă����B�Ԕ��̍��ˉ��������Ă��Ĕ��A�������l�W�o�i����ԏ�܂ō炫�܂����B

16�K����̒���

����͂U�K

�����̖@�ʂ�

���Ղ�̎n�܂�

���W�Y��
�@�����̉��A���h�ȃ^�V������������܂����B�ȑO�A�Ԕ��̍��˂̉��ɍ炢�Ă����̂��v���o���`���Ă݂�ƁB����܂����B��̕S���g���炢�Ă��܂��B�u���[�x���[�̎��n���n�߂܂����B���܂�������悤�ł��B





�@����Ɛ��ꂻ���B���͂܂������Ȃ̂ŁA��`�R�ɍs�����Ƃɂ��܂����B�������ƁA�̂��肪�A����ς�u�������Ɓv�Ƃ����Ȃ��̂͂����̂��ƁB�܂�����������ė\��Ƃ͈Ⴄ�����オ���Ă��܂����B�ԓ������]�Ԃ������āA�r�����x�����܂������ɂȂ�Ȃ���オ��܂��B��������A��`�����ɒ������͂������R�����킩��Ȃ��B�匠���ɍs���āA�W�]��ɂ��s�����ǓW�]�͂Ȃ��B����������Ǝԓ��ɂ��ǂ�����A�R���͂������Ƃ����W�����B�ʐ��{�ɂ���āA��`�_�Ђ͂��ꂾ�A�ŁA�R���͂ǂ����H�R�����ڂ��Ă�n�}�������邪���������ĂȂ��B�����߂������B���傤���Ȃ��̂Ō��������ĕ����o���Ƃ����ɕW�����o�Ă���B��������ƒ����܂����B�v���ĕ��ʂ������܂����B�����A�Ƃ��ƂƋA��܂��B����̓X�C�X�C�B�P���Ԉȏォ�������̂��P�O�����傢���炢�B������̂ŕs���ł������A����ς�Ԉ���Ă܂����B���Α��ɉ���Ă܂����B�ł����ʂ悩���������B���Ԃ̓��̉w�ŕٓ����ĐH�ׂ܂����B�Ȃ�Ƃ��A���B�v���Ԃ�ɐ���ĔM���Ĕ��܂����B

�R���͂ǂ��H

�����

������

�����A��������

�n�N�r�V���H
�@�钆�J�̉����������Ă��܂������A�����Ď���Ɏ~��ł��āA���炭���������B�����������͍��J�̗\��B�s���Ă������Ƃɂ��܂����B�����̉��͈��Ń^�V���������ɂ傫�ɂ傫�Ƒ����Ă��܂����B��N�N���^�P�������Џ@�|�Ǝԓ��̊ԂłR�p�����肻���Ȃ̂��������̂Ńp�V�����B���ăL�k�K�T�^�P�B�k�ʂւP�Om���̂Ƃ���ɍ���^�}�S�����������ǁA���A����ςɏo�Ă܂����B���ɂ͂Ȃ����Ƃ���������āA�Ȃ��Ȃ��Ɩ߂肩����ƁA��H�o�q�����܂����B




�@���Ԃ͓܂�̂悤�ł��B���Ԃ���v���낤�ƁB�܂��J�m�R�����̗l�q�B�������܂��B�ł��Ƃ�����菬�����Q�B�^�V�������͂���܂����B�|�c�|�c�ƂT�͊m�F���܂����B���������A���������ĂƁA���ԏꉺ�̐Βi�̉A�����Ă���ƁA�O��ƈႤ�ꏊ�����A�傫������悤�Ɍ����邪�A����ł��傤�B����������B�~���đ��i�N���^�P�j�B���Ď��̓E�X�L�k�K�T�^�P�B��q�����܂����B���傭���傭���Ă�݂����B






�@�炫�n�߂Ă���̂������܂��B���ʂ̑傫�Ș@�͖w�ǂ��܂��Q�ł������A���N�@�Ɩl�̍D���ȕ��ܘA�͂��������ł����B�W���s���N���Q���A�J�Ԃ���Ƃق�̂艩�F�݂�тт����ɁA�����ł��B



�@�w�Lj�a�����Ȃ��Ȃ����悤�����A�R�N�����̗l�q��������łɂ�����Ƒ��̒��q���������ƍs���Ă��܂����B�炫�n�߂Ă��܂��B����ɂ��Ă��n���ȉԂł��B��R�[�X���オ���āA�P�̐V�����g���ĒY�ăR�[�X������Ă��܂����B�����̃��}�����͖w�Ǘ����Ă��܂��Ă܂����B���͉�������v�����ł����B�܂��A�ڂ��ڂ��ƁB






�@�Ăł��˂��B������ƙy���߂ł����B�ł��Ԃ��Ȃ��~�J�B�Ԃɍ��������Ȃ̂Łu�^�C���E�������o�[�h (Time Remembered)�v�����ɍs���܂����B




�@�o�Ă���ƌ����m�点�����܂����B�Ȃ�قǁB�ł��X�q���Ԃ����܂܂ł����H�^�}�S������܂����B�g����������n���ăW���K�C���@��͏I���i�����̕����c���Ă܂����j�B�~�J���肪�x��Ă��܂��B�L�^�X�V�ł��B


�@�قڗ\�z�ʂ�B�r�̂��̃C�`���N�\�E�͍炢�Ă��܂����B�E���K�T�\�E���炢�Ă��܂������r�̟��̂����B���Ƃ��Q�ł��B�N���L���\�E������炵���̂ŒT���̂ł����A�Ȃ��Ȃ��B�ł��A�����Ƃ���܂����B������������͉߂��Ă��܂������B��������������g���{�\�E���炫�����ł��B���傤�͒����I�^�N�������ς����Ă܂����B











�@����ς�C�`���N�\�E���Q�A�E���K�T�\�E�͒r�̓����̂����m�F�B�o���K���[�ƒr�̊Ԃ�����ɂ��������������킩��Ȃ��B����ɂ���ăo���K���[�ƒr�̂���������낤�낵�Ă���Ə�̕�����u�E���K�T�\�E�������Ă��`�v�Ɛ����B�����I���������s���Ă݂�ƁA����܂��A�������A�炢�Ă͂��܂���ł������B�������g���{�\�E���Q�����傱���傱�Ƃ���܂��B�v��ʎ��n�A�ӂ��ӂ��ӂł��B���N�͂W�X�V�s�[�N�̃��}�{�E�V���s��炵���ł��������r�̂�����Ȃǂ��ꂢ�ɍ炢�Ă��܂��B���}�c�c�W�͍��������̂悤�ł��B
�@���傤�͕ςȒc�̂���g�����̂��͂��߁A���̂ق��ɂ����̂����l�������ē��₩�ł����B���̕��͂Ȃ�Ƃ�����Ԃ��o�Ă��܂�������͉_���������Ă��Ă�����Ɣ��������炢�B

���̂��݂ł�

������Q

�����ł���

�I�I�g���{�\�E��

���E�Z���S�P

�����{

������

�����ɂ����̂�

����Ȃ̂�

����́H

�܂����ꂢ
�@�����Z���^�[�̃q�c�W�O�T�������悤�Ǝv���Ă����Ƃ���ɓ��@�B���傤���Ȃ��̂Ŏʐ^���B





�@��������Ȃ����̂ʼn��߂Ċm���Ɍ����Ƃ���ցB�Ƃ��낪�����J�r�������Ă��Ă��܂��B�h�����Ďc���Ă���̂�����܂����B���ԂȂ����ԂȂ��B������̃R�N�����̗t���ς��B�ǂ���狎�N���������炵���̂ł����E�E�E






�@�Ԃ�����悤�Ȃ̂ň�m������k�������[�g�Ƃ����̂Ŕ����R�ɍs���܂��B�n�}�������čs���ĂȂ������̂œ�����T���̂ɂ������܂����B�����ɏオ���Č����[�O�p�_�܂ł������ɍs�����炠�Ƃ͏����ȃA�b�v�_�E�����J��Ԃ����������ł��B�R���̉��ŏc���H�ɍ��������甒���R�ւ͍s���������R�̕��ɏ����s������ň�m���։���܂��B���x�͒J�B�ꉞ�ѓ����������ĉ��H�Ƃ͂����ĕς���Ċɂ₩�ɉ����čs���܂��B�k��������̏�����O�ɃE���m�L�������ς�����܂����B

�E�c�{�O�T

�L�L���E�\�E

���}�O���̎�

���L�m�V�^

�~�Y�^�r���R

�n�i�C�J�_�̎�

����܂�

�E���m�L

�~�Y�^�r���R

�E���m�L

�E���m�L

��
�@����ԂɌ����Ƃ��͊J���Ă��܂���ł����B����������ƁB�Ȃ�ƂP���Ԍ�Ɍ�����炢�Ă���ł͂���܂��B�т�����ł��B����ƉԂ̐F���킩��܂����B���̂��Ƃ͎����玟�ɊJ���āA�S���ŋ�ւɂȂ�悤�ł��B

5/24/�y

5/30/��

6/1/�y
�T���P�U���i�j�F�㍂�n�`���b�a
�@���{��`����V���g���o�X�A��ԁA�o�X�Ə��p���ŏ㍂�n�ցB�������x��܂����B������Ƒ����Ǝv��������Nj@���ł����ɂ��Ă����Ă悩�����B�㍂�n�͐l���܂�B����Ȃ̂͏��߂āB���̎����ɗ���̂����߂Ăł͂��邪�B�܂��Ă��܂��B�����͓���܂ŁB�j�����\�E�͂����ς�����܂����܂��Q�Ȃ̂��܂��Ă��邩��Ȃ̂��A���܂�J���Ă��܂���B�A��Ɋ��҂��܂��B���T���������ς��o�Ă��Ă��܂����B�������Ԃ�V�A�ꂪ�����B���������G�߂Ȃ̂ł��傤���B
�@���b�a�ł�炶��E���܂��B�Â��ŗ����������A�Ȃ��Ȃ��悢�h�ł����B�l�����Ȃ��̂ł�����O�H������������Ȃ��Ƃ͂���܂���B�V���v���ł��������͋C�̂���A���肰�Ȃ��������ȏh�ł����B

�����Ȃ����������

�Â��ȏ㍂�n

�n�V���h�R��

�j�����\�E

�����ς�����܂�

�����̉Ƒ�

�����Ⴞ��

�����܂���
�@�����V�C�B���̘e���o����B�Ȃ��Ȃ��̋}�o�ł��B�Q�O�O�Om�n�_�ŋx�e���āA�����i�Ƃ���ŃA�C�[�������B�������炪�����̂ł��B�P�������炻��������̂ł��傤���B�������Ђ�����i�݂܂��B�悢����悢����B�悤�₭�����R�ɓ����B�쑤���J���Ă��܂��B�_�������Ȃ��Ă��܂����B��������̂ł�����Ɗ����B�������߂���ƁA�ŏ�������Ɖ����ēo��Ԃ��܂����A�ɂ₩�ȃA�b�v�_�E���ɂȂ�܂��B�d���m�r�̟��ɓo��Ƒ��������܂��B���̎c��ł����x�e�B�₪�ď������A�����ĕ䍂�A��Ƒ������ꂢ�Ɍ�����悤�ɂȂ�ƁA���Ƃ͂��������Ɍi�ς��y���݂Ȃ���������i�݂܂��B�����̎�O�̏������u�������x�̂悤�ł��B���܂��B�����̂��h�͒����x�q���b�e�B����ς�������ł��B�����ł��ˁB�h���G���A�ɒg�[���Ȃ�������Ɗ��������ł����B���A���ꂩ��z�c��������Əd�������B

������

�}�C�d���\�E

�C���̂������ł�

���悢��o�Ԃł�

�����Ƃ���Ȋ���

�����R

�d���m�r

����������

�䍂�A��

�����x

�悤�₭�S�[����

����

�����x�R������

�������

���������܂�
�@�����������V�C�ł��B�܂��Ő�������B���䍂����������ƌ����܂��B�ړI�B���ł��ˁB����������߂��A�r���ʼnו����f�|���A�O�p�_�i�������x�j���߂��A�����܂ōs����������Ԃ��܂��B��������܂Ŗ߂����牺��B���炭���ăA�C�[���𒅂�����čs���܂��B�U��Ԃ�Ƌ��낵���}��B�o�肶��Ȃ��Ă悩�����B�����ԐႪ�ɂ�ł���̂œ��ݔ����Ȃ��悤�ɐT�d�ɉ���čs���܂��B�Ⴊ�Ȃ��Ȃ�X���ɂ�ł悤�₭�����B�������`�B���[������H�ׂ��瓿��܂ł����ꓥ��B����̂��h�͓��B���̊Ԃɂ����j���[�A���A�ł��������B�܂��������ǁB

���̏o

�x�m�R

�����x

�o��

�䍂

��

��x�R�E���

�����Ə�O

������V������

�C���q�o��

������

�ՎU�Ƃ�������

���܂�

�t�L�m�g�E

�j�����\�E

�����

�j�����\�E

�l�R�m���\�E

���}�G���S�T�N

���J��
�@���悢��ŏI���B����㍂�n�܂ʼnԂ��y���݂Ȃ���������Ɩ߂邱�Ƃɂ��܂��B���҂ǂ���j�����\�E�͂R���O���J���Ă��܂��B�����ł��B���T��������o�Ă��Ăɂ��₩�B�Ȃ��Ȃ���i�݂܂���B���_���o�Ă����ɃT���J���E�̎ʐ^���B���Ă���l�ɏo���킵�܂����B���b�L�[�ł����B�R���Ԕ��������Ă悤�₭�㍂�n�B�ǂ��ɂ������̎��Ԃ͊m�ۂł��܂����B

�A��܂�

������

�ȂɁH

�~���}�L�P�}��

�V���o�i�G�����C�\�E

�e�q�A��

�`���������\�E

�j�����\�E

�O�~�ł�

�G�ɂȂ��

�~���}�J�^�o�~

�G�����C�\�E

������

�E�c�M

�T���J���E

�X��

�c�o���I���g

�C���{�^��

�E�X�o�T�C�V��

�A�b�v

�q���C�`�Q

�������

�����������
�@���]�Ԃ𑆂��Ԃ�ɂ͕G�ɉe���͂Ȃ��悤�Ȃ̂ł��B�炢�Ă��܂������Q���܂�����܂��B�����Ƒ�����ł��傤�B�v���Ԃ�Ƀj���[�L�V���E�̎ʐ^���B��܂����B�Z���_���̉Ԃ��炢�Ă��܂��B�A��ɋ߂���ʂ�̂ŁA������J�����V�����Ȃ����Ɗ���Ă݂܂������A��܂���ł����B�N�T�t�W���т����肷����炫�ق����Ă��܂����B





�@�m���ɏ[�����Ă��Č�����������܂����B�Ƃ��ɔӔN�߂��̍�i�͌�����Ă����앗�Ƃ͂܂��Ⴂ�A��������\�N�Ɠ����悤�Ɍ��Ɍ����Ă����Ƃ͒m��܂���ł����B�����̌��A�n���̌��A�H���B����ɂ��Ă��A�����������l�����ɂ͒������A��r�I���₩�Ȑ��i�������悤�ŁA�u�����킹�Ɏv����v��Ɛl����S�����Ă��܂��B
�@���炿�˂̂��܂͖��Ȃ�/���̍������ʂ�����/�ɂ܂��������̎p/��Ƃ������̂�̐���/���̕�����͂��܂���/�ʉe�̂�����/���̂����������Ȃ��̂�����



�@�L������������炵���̂ōs���Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B���c�n����オ��A�����R�Ɉꉞ����āA�c���H������܂��B���̏c���H�A�Ȃ��Ȃ����������ōD���Ȃ�ł����A�b�v�_�E���̘A���ŏ��X���܂��B���ǔ����R�܂ōs���āA�A��́A�������Ƃقڕ��s�ɑ����Ă���ѓ��𖾐��R�߂��܂Ŏg������Ă��܂����B
�@���Ă��ړ��ẴL�������ł����A�ŏ��ꊔ�A���̂��Ɛ������h�Ȃ̂��B�悩�����ł��B�v���������V�������������܂����B�^�c�i�~�\�E�͂ǂ����j��ނ���悤�ł��B�Ԃ̐F�Ɨt�̌`�Ⴂ�܂��B���̎����Ƃ��Ă͌��ʂ��������A���R�A�߉ށE��O�Ȃǔ������ʂ̎R�X�����ꂢ�Ɍ����܂����B

�炫�n�߂Ă��܂�

�^�c�i�~�\�E

�����I

�܂������I

�V�����������I

�{�����[��������

�߉ށE��O

���R

����͍炫�n��

�ѓ��ɂ�

�݂��Ƃł�
�@��J�R�[�X�̗ѓ��o�������猎���R�ɏオ��r���̃M�������E�\�E�̐���������ɍs���܂����B�Ƃ�ł��Ȃ��ɂȂ��Ă��܂����B�����炱����Ɍł܂��ėї��B�M�������E�\�E�̐X�Ɖ����Ă��܂����B
�@����������č��Ǒ�Ђ֍s���ƒ��������s�ł��Ă��܂��B���݂����H����Ⴄ�A���I������т�����B�ł����ꂭ�炢�͂Ȃ܂�����낢�����Ƃ��ƂŒm��܂����B�A��͓�ʂ��牜�m�@�o�R�ŏҊ��r�։���Ă��܂����B







�@�����͉J�����A���傤�ǂ悢���݂����Ȃ̂ŕ��U���܂����B�����͓��Ղ肾�����ł��A�l�������ł��傤�ˁB




�@���傤�ǂ悢���݂����Ȃ̂ŕ��U���܂����B�����͐l�������ł��傤�ˁB





�@�����͂����Ƃ͂�����ƈႤ���[�g�ł��B�g���x���獂�Ǒ�ЁA��ʁA������x�A�X�ь����A�����A�_�Đɉ����Ęh�m���x�������Ďԓ��ɏo����g�t�J����Q���ɁB�M�������E�\�E���ڂ��ڂ��o�Ă��Ă��܂��B�ォ�璭�߂��c�c�W�͂قږ��J�B





������

���݂���

�t���傫��

�܂�ŃZ�b�R�N�̖�
�@���ꂩ��P�O���A�v�킭�ʂ�炢�Ă��܂����B�����A�t�̊��ɉԂ����Ȃ��ł����ˁB���������V�����������������͂��B�ق�ˁB�L�����v������̃G�r�l�͂܂��ł��Q�B

�炢�Ă�

���ނ���

�T���߂ł�

�o�q

��������o�q

�O�Z��H

�z�E�`���N�\�E

�N�����W�H

�X�~���`

���������̂Ă܂�

�N�����W�H

�j�V�L�S����

�X�~��

�����̋�

�V�R

�܂��炢�Ă��܂�

�M�d���Q

�X�~��

���C��

�Z���{������

�y���݂ł�

���ꂢ

����

��������

�����Ȃ��Ł`
�@�����āB�قڌ����������悤�ł��B



�@���̎����A���낻��s���Ă����˂B�O���͎ԓ����g���܂��B�^�j�M�L���E���B���Ă���ƁA�A�~�K�T�^�P���B���ł���ƁA�߂��ɂ���킠���B����Ȃ̏��߂Ăł��B����~�Y�^�r���R����������Ȃ��B�܂��ł��傤���B���R�����ɓ����Ă��炭������}���V�O�T�ƃq�g���V�Y�J�̃R���{���[�h�B�����̃q�g���V�Y�J�͂܂��炢�Ă��܂����B���̓x�j�c�`�J�����V�A�̔��ł����A���Ȃ��B�ьG�ɂ����Ȃ��������B���N�͊O��N�H�����h�E����������t�c�E�ɂȂ�܂����B�M�������E�\�E������o���i�����͋C�t���Ȃ������j�A�i�����̃G�r�l���炢�Ă���̂�����܂��B�����Ă��̊Ԃɂ��V�̋G�߂ƂȂ�܂����B










�@����S�O�O�N�̃V���N�i�Q�����ɍs���܂����B���̖͒x���悤�ł��B�܂��Q�ł����B�C�m�V�V�����̍���J���ēo�R���ɓ��邠����܂ōs���Ă݂܂����B�����ȗ���̘e�̃V���E�W���E�o�J�}���炫�ق������Ƃ��͂Ȃ��Ȃ��ł��傤�B���M�ƗV��ŏW�������Ƃɂ��܂����B





















�@���܂�V�C�͂悭����܂���B�C�����Ⴂ�B���҂��čs�����̂ł����܂��ł����B���傤���Ȃ��B�ړ����đ��R�ցB������͂��������v�B�q�g���V�Y�J���炫�n�߂Ă��܂����B��������C������ł��܂��B�_��Ƒ��ǂ̂��ꂢ�ȃV���G�b�g�A�L���C�������܂��B










�@�����č��ǐ�ցB
�@��̐Ν͂��炢�Ă��܂��B�q���̍��悭�o���ėV�A�Â��T�U���K�̏�ŁB





�@�[�̗��k���������X�^�[�g�B�܂��̓q�g���V�Y�J�̊J�������A�C�`���N�\�E�̗t�A�������L�c�l�m�J�~�\���̗t�A���}�����\�E�A�G�C�U���X�~���ŏ����B�Ԃ��Ȃ���C�ɃM�A�̓g�b�v�B�V���o�i�l�R�m���\�E�ƃn���g���m�I�ɃT�o�m�I�A����킠���B�������T�r�i�炵���j�������ς��ł��B�R�K�l�l�R�m���\�E�ɁA�t�E���P�}���A�`���������\�E�A���}�A�C�E�E�E�@����Ɨѓ��o�����ł��B���ꂩ��͋}�o�B�킩���Ă͂��邯�ǂ����o��ł��B
�@�R���ł�����H�ׂ���߉ފx�ցB�Ő��Ƀ}���T�N���炢�Ă��邻���ł��B�܂��c�������h�E�̗t���m�F�B�}���T�N�͍炢�Ă��܂���������Ɖ߂��Ă��܂��ˁB�����̓W�C�\�u���炭�悤�ł��B�_�������Ȃ��Ă��܂����B����Ă���\��ł́H�R����O�̑傫�ȃj�Z�s�[�N���z���Ō�̋}���o��ƎR���B
�@���A���Ƃ͉���ł��B���܂łɂ���ׂ���P���ł������L�U�T���L�͈͂ɌQ�����Ă��܂��B���낻��炫�����B�G�C�U���X�~�������ꂢ�ł��B��z�ѓ��ɂł���A�D���悤�ɗѓ������x������Ȃ��牺��čs���܂��B�I�I�L�c�l�m�J�~�\���̗t���т�����ł��B����ɁA�����ɂ����҂ǂ���A������҈ȏ�Ƀn���g���m�I�A�T�o�m�I�A�V���o�i�l�R�m���\�E���A�������蓥��ł��܂������Ȃ��炢�B���}�G���S�T�N����������B���T�r�̉Ԃ��炢�Ă��܂����B
�@�Ō�͗ѓ������B�����Ƀq�g���V�Y�J�A�@�ʂɃC�`���N�\�E�̗t�B�Ԃ��������L�u�V�B�Q�b�v���o�����B�����o���Ă܂����ǂˁB�����_�_���̍������܂��ɕt���Ă��܂����B






























�@���ҐU�̎ΖʂɃs���N�̂����܂肪������B�T���ɍs���Ă݂܂����B���ҐU���{�s�P�O�O���N�L�O�������肻�̎��ӂɍ����A����ꂽ�悤�ł��B���������猩���Ă������͂��ꂾ�����̂��B�����Ȏ�ނ�����̂Ŕ����ȊK���������ł��ˁB�����R(452m)�ւ̓�������悤�ł��B






�@�u�������́v�Ɠǂނ悤�ł��B���[�g������悤�Ȃ̂Œ����ɁB�������E�@���Y�̓o���������ѓ��@���Y�����W���܂Ōq�����Ă���悤�ł��B���F�a�@���ɂɃ`�������߁A�オ���čs���܂��B�ѓ��ɏo����ѓ������B�ѓ��I�_�ɂȂ�A�S���̂��܂ōs���܂������r�����łȂ��Ȃ��߂Â��Ȃ��B�W���͂������������Ȃ̂ɁB���߂ď��������Ԃ��Ƙe��������B���ꂾ�B�s�������A�Ɗ��҂��c��ށB�Ȃ�Ƃ��S���̂��܂ōs����������ȏ�i�߂Ȃ��B����ς肾�߂��B�������A���[���Ƃ���������Ă���ƁA�Ȃ��A������Ɠ��������Ă����B�����炯�ł͂��邯��ǁA�����B�s�������Ȃ��낤�B�W���ւ̓��ł͂Ȃ��������w�U���֏o�铹���B�����B��������ԓ��ɏo�Đ��ʂ���W���ɍs�����Ƃɂ���B�Ƃ������ƂłȂ�Ƃ������̖ړI�͒B�����܂����B�����B
�@�召��W���F�Γ�ԋ��Ƃ������h�ȋ���n��Ƃ���܂����B�����ȏW���B�Ȃ��q�̓I�ŕʐ��E�A�Ƃ����̂͑傰�����ȁB�ł������ł��B����������S�O�O�N�Ƃ����V�R�L�O���̃V���N�i�Q������܂����B

�o��

�i�߂Ȃ�

�����ɏo��

�W���̒�

����������

�p��������

���̓S����

�I�����_�K���V

�ۂۂ���

�̂ǂ��ł�

�ւ��`
�@�ʐ^���d����ɁB�ߑO���͑��R�̘[�̍��ƃo�C�J�C�J���\�E�B�Ȃ�Ƒ��������Ă��܂����B�k���������B�ߌ�͌����r�֕����āB












�@�V���������͂܂��Q�ł����B��������̏�����Ɍ����ȍ��������Ă��܂����B�A��Ɋ��܂��B�������班���������Ƃ���A�����炭�����ł��傤��������Ƃ��ז����܂����B�f���炵�����ł����B�����Âߌl�̍��n��ł��ˁB�����ăo�C�J�C�J���\�E�B�炫�ق����Ă��܂��B���ǎR�o����̌����r�̍��������ł����B�߂��ɏZ��ł���l�������܂����B�ʐ^�H���ɐ\����܂��A�炵�Ă���܂��āB�����͓��ׂ���\��ł��B
�@������㕪�����ȁB�ł����������ƕ����Ă��܂����B�c�O�Ȃ���x�̓쑤�̎}���������荞�܂�Ă��܂����B���₵���`���E���v���[���̎}�Ɏ~�܂��Ă��܂����B
PS�@�`���E�́u�c�}�L�`���E�v�Ɣ������܂����B�i10/4/2021)





�@�����r�̍����݂āA�X�ь������猎���R�B���Ǒ�Ђ���Õ�a�Ղ��o�ĉ��q�r�ցB�߂��āA�A��ɑ�w��ׂ���āB












�@����̗l�q���ƍ炢�Ă��邩���A�ƕs��������s���Ă݂܂����B�Ԃɍ����܂����B�Z���炫�H�㔼���͂܂��Q�݁B�N�����܂���B�Ƃ��߁B��Ɠ��ɂ̓��}�U�N���������������B�t���ƐԂ��ۂ��̂Ƃ���܂��B�R�u�V���B�L�����\�E�͑����Ă���B�o����ɂ��R�u�V���B






�@���₩�ȓ��a�ł��B����ȓ��͎��]�Ԃ��R�H�ԗ��ʍs�~�߂Ȃ̂ŌÏ��ѓ��̓�����������܂��B�@�ʂɃ��}�����\�E�A�R�N����������܂��B�A��ɂ́A�L�P�}�������܂����B�R�O�����Ō܍��ڒ��ԏ�B�l�R�m���\�E�͂�������B�V���o�i�ł��傤���ˁB�T�o�m�I�͈ꊔ�����B�`���������\�E���炫�n�߂Ă��܂��B�R�����ɂ̓z�\�o�R�o�C���B�ЂƂЂƂ����Ⴄ�Ƃ��낪�ʔ����B


















�@�k���̑垸(230m)����オ�螸��(160m)�֎��Ă݂悤�Ǝv���܂��B�k�ʂ̃��[�g�͏��߂Ăł��B�哻(300m)�����菭�������͒Z���ł������x�͒Ⴂ�B
�@���̓��ł��B�����Ȃ�V���E�W���E�o�J�}�������B������������܂��B�J�𗣂��܂œ_�݂��Ă��܂��B���炭����ƖX�̊Ԃ��甒���Ԃт炪������悤�ɂȂ�܂��B�����Ƃ���͎̂}�̊Ԃ���h�����āA�߂��݂̂͂�ȍ����Ƃ���ɍ炢�Ă���̂Ō��グ��Ƌ��w�i�ɍ����ۂ��Ȃ��Ă��܂��B�Ȃ��Ȃ��v�킹�Ԃ�ȉԂł��B�哻���[�g�ƍ������A����������߂�����Ԃ��Ȃ��R���B�R�����琼�֑����������������Ă݂܂��B����ς艓���Ƀ`�����ƁA�n�ʂɉԂт炪�����Ă����������āB���邭�C���̂悢�����ł��B���낻������Ԃ��ĉ���܂��B��������垸�����r���ɂ��V���E�W���E�o�J�}�����܂����B




















�@�ƌ����ڂ������ł��傤�B����ς�ɏ����Ă܂����B���V�R(127.2m)�̂��Ԍ��̏������i��ł���悤�ł��B������ɁA�ɁB�ƂA���āA�ÉĂ����n���āA�}�[�}���[�h������āA�W���K�C����A���āB�t�͖Z�����B





�@���̂Ƃ����R�ɂ��܂��Ă����̂ŝX�˂Ă͂��܂����Ǝv���A�J���オ�������A���@�����f���ɁB�v���̂ق����҂��Ă���܂����B�~�c�o�c�c�W���炫�n�߂āA�I�^�}�W���N�V�����݁A�����T�L�P�}���ʂ�Ƀq���I�h���R�\�E���炢�Ă���Ƃ͍��܂Œm��Ȃ��������A�L�����\�E���ڂ��ڂ��B�o����̃~�c�}�^�͖��J�B












�@�����̑|���B���n�����炢�Ă���ƌ���ꂽ�̂Ō��Ă݂܂����B�悢�ł��ˁB�ƂA���ĔӔ��M��������{�A�ƃC�`�W�N��A���܂����B�y���݂ł��B



�@�̂��肪�\�z�O�Ɏ肱����܂����B�܂��͎핟�������R�ցB���̂��Ɣ������[�g�͂Ƃ炸�A�O�̂��ߍŏ��ɍ~������Ԉ�����Ƃ��납�牺��Ă݂܂����B����ς蓯���Ƃ���͒H��܂���B���悤�Ȃ�t���[�X�B�J�ɉ��肽�牎�x�ւ̃��[�g���オ��܂��B�����͍����Ȃ̂ŕ���#1���߂��A�������傢����l�߂Ĉƕ��܂ōs���܂��B���A�Q�T�Qp�ւ̕���#2��������ꂸ�s���߂��āA�W�]�̂����Ƃ���ɏo���B���x�ւ̃��[�g��ŁA�����ɏ�����Ƃ��낾�����悤�ł��B���傤�ǂ悢�̂łƂ肠���������B���ĂŔ����������n���o�[�O�ƃ��[�����ŕ������炦������J�֖߂��Ă�����x�����T���܂��B����܂����B�����B�悤�₭�Q�T�Qp�B����ς�Ȃ��Ȃ������Ƃ���ł��B��������オ�����}��������͉���܂��B����ς�댯�ł����B

��������

�����Q�T�Qp

���x

�y��R

����������

�N���L�H

�q�T�J�L

�k�[

�ьG�R�Ƒ��v����

�����̈�\�H

����ė��܂���
�@�핟�������R�ɏオ��A�ؒʂ������ɍ~��A���x�̕��֏����o��Ԃ��A�Q�T�Q�s�[�N�ւ̕���#1�����������ďオ��n�߂�B�e�[�v�������B���Ƃ̓e�[�v��H���āB�ł����낵���}�ł��B���[�Ȃ��B�������A�͂߂�}�⑫���T���̂ɋ�J���܂��B�悤�₭�Q�T�Q�s�[�N�B���ƊÔ[���̃V�z���Ɩ����ƊÔ[���̏����p���ł�����Ƃ���x�e�������ɐi�݂܂��B�����ȃs�[�N����������k�ɒ��������œW�]���y���߂܂��B�k�[�̃s�[�N����������Ɛؒʂ��i�ƕ��j������A�܂��Ȃ���ʼn��x����̃��[�g�ƍ����B���̂܂ܑ������Ă��܂����B�S�R�c�o�L�̎R�ł��B����ς胄�u�R�M�����Ȃ��ƃt���[�X�͌�����Ȃ��悤�ł��B���傤���Ȃ��B
�@PS�@�V���������Y�����܂����BLimited�V���[�Y�̒��Ŏg�������Ȃ̂������܂����B

�}�ł�

�����Ƃ�����

������Ƃ����

����Ƃ�������

�H�ׂ����ł���

�傫�Ȗ̑�

����

���ǂƑьG�R

�y��R

���[�Ə�R

���[�̃N���}�o�i

���ׁA70/2.4
�@���_��ς���ƁA���邢�͗����ʒu��ς���ƕ��i���ς��B��������i�������Ă���B�T�ώ҂Ƃ��Ă݂邩�A��ЎҁE�]���҂̗��ꂩ�猩�邩�A���邢�͍��E�א��҂̗��ꂩ�猩�邩�B
�@������悢�f��ł��u���l�v���Ȃ����̂�����B����A�u�悢�f��v�͖��l���Ȃ��̂����m��Ȃ��B�l���邱�Ƃ������邩��B�ǂ��ł��傤�H



�@2017�N�̋�B�k�����J�ōL�͈͂ɓy�Η��̂̔�Q�����Ēʍs�~�߂������ł��������Ēʂ��悤�ɂ͂Ȃ��������ł��B���n�̎�O�R�L������O��������n�߂܂������A�ԗ��ʍs�s�\�͍Ō�̂P�L�����B��Q�̐������_�Ԍ��܂����i�O��͂P�V�N�̏t�ɗ��Ă܂����j�B












�@�C�J���\�E�͂����ԑ����Ă��܂����B�A�}�i�́H�N�����̂͂����ƍ炫�ق����Ă��邾�낤�Ǝv���Ă����Ă݂�ƁA�Ȃ�ƁA���܂�炢�Ă��܂���B���̑O�̕����悩�����B�ł͏�̔��́H������͑����Ă��܂����B
�@���n��̌��ւɂ͌�œ��Ə��������Ă������Ă���܂��B����ɂ�����������ǁA�����̂͌�_���Ə����Ă���܂��B�����Ă݂�ƁA�߂��Ɋω��������薾���A������͂P�R�N�Ɉ�x�̌�J���B����͗��̐_�Ђ̊W�ňꌬ������_���������ł��B







�@���c�����d�����������Ƃ��܂��Ē��O�ɂ͉���Ă�����肾�����̂ł����B�܂��핟���ցB�Ȃ��Ȃ������ꂢ�Ȏ��ŁA���͋C�̂����揊������ɁB�E���肪�o����B
�@���[�g�ɂ̓��[�v�������Ă���}�ȂƂ���͊K�i������B���w�H������ˁB���R�т��C���������B�Q�O���ŎR�����ցB��������Ղł��B�s����������Ē[����[�܂łS�O�Om�ʂ��ȁB���悢�悻�̐�i�݂܂��B���Ȃ�}�ȉ���ł����s�������Ȃ̂ŁB�ꉞ�e�[�v���������A�ŏ������������i�����ŊԈ�������߂��Ƃŋ�J����͂߂Ɂj�B�܂��ړI�̖x�ɒ����Ȃ��Ă��O��ʂ�����̓��ɏo�邾�낤�ƁB�͂��A�o�܂����B����������߂Ėx�֍s������T���܂��B����炵����������߂ďオ���čs���܂��B�i�X�Ɣw�̍����V�_�ɑj�܂�č�����ɂ߂܂��B���ƂQ�A�Rm�ŗŐ��ɏo��̂ɒ��߂悤���Ǝv�������B�o���`�B���ꂢ�ȓ��B�R���Ɣ��̕��ɉ����čs���Ɩx�B�R���ɖ߂��Ă��������ǁA������m�F���邽�ߒJ�̕��։���܂��B�p���̂Ƃ��납��v������菭����O�ł����B���A�߂�܂��B�R���̂�����O�Ɍ����炵�̂����₪�������̂ł��̏�ł����B
�@�A��͂��������������B����ɁA�ƂɋA������t���[�X�𗎂Ƃ��Ă��Ă���̂ɋC�����܂����B���ڂ��M��ځA����R������A�������ʂɖI�E�E�E

���P�G�R�Ɠ��̌G�R

�핟��

������

���������ł�

�����A����G�R

���w�H

�R���ł�

�s�̋���

�ʂ�

��

�L�N���Q

�l�Ƃ̂���

���x�Ɠy��R

�؉ԃ��[����

�錴��
�@�����͓��̐ߋ�A�ЂȍՂ�B������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B��ƁB

�ю�����

�����̖�

������@���

���n���ɏH�����G

�����~

����l�`

�䏊����

�G���x�[�^�[������

�܂��܂�����

����
�@���x�̂�����Ǝ�O�ɏ�R�։���čs����������Ƃ����̂ōs���܂����B�y��R���牎�x�ւ̏c���H�̓z���g�ɂ����ł��ˁB����A����܂����B���x�܂ňꉞ�s�����Ƃɂ��܂��B�����������Ǝv������A��O�ɑ傫�ȃj�Z�s�[�N�B�����ȃs�[�N������B�܂�Ԃ��ĕ���֖߂艺��܂��B����A�Ȃ��Ȃ��悢�A�Ǝv�����͓̂r���܂ŁB�A�тɕς���đ��ꂪ���܂�悭�Ȃ����͂����肵�Ȃ��J������čs���܂��B�X���ɂ�ł��邪�A���ꂩ�炪�����B�r���p����߂���B�����炭��R�̐��������Ă���̂��낤�B�����܂ŗ��Ă���Ǝԓ����o�Ă���B���̌G�R�̌��ɏo�Ă��܂����B���`�����тꂽ�B��R�̎��ӂ͎j�Ղ������ς�����悤�ł��B�G�t�s�R�̉���ʂ��Ė߂��ė��܂����B��R�̐�������郋�[�g�������Ĕp��������ɂ��̕���炵���Ƃ��������܂����B�ق�Ƃ͂�����ɍs�����������̂ł����A�m���߂܂���ł����B
�@PS�@���x�̓T�b�_�P�ƌĂԂ悤�ł��B��R�R���͏�Ղœ��R�s����݂����ł��B

�����ł���

���ꂾ

������

�j�Z�s�[�N

�Ȃ�

�������

���V�_�Ђ�

��R�Ɠy��R

�N���}�o�i
�@�����̂Ƃ�����k�̕��ɕW��������̂ōs���Ă݂��B�o�R��������̂��Ǝv������A�X���`�b�N�L��֍s���ԓ��ł����B�r���ԓ�����Q�C�R�O�Om�������Ƃ���ɂ��鉜�m�@�ɍs���Ă݂܂����B���������傫�������B�ԓ��ɖ߂��ăA�X���`�b�N�L�ꂩ��R���ցB�����������ł��܂��B�A��ɃG�C�g���_���Ɋ��܂����B�������t�ł��B



�@����ыƎ�����ɃI�E�������炢�Ă���Ƃ����̂ōs���Ă݂܂����B���̂��ƃA�}�i�����ɍs���܂����B���̂��̓C�J���\�E���������Ă��܂����B�����ƍ炫�n�߂Ă��܂����B�A�}�i�̂��Ƃ̓G�r�i�E�E�E










�@�炢�Ă���Ƃ͎v���܂���ł����B�o��n�߂̔��̗l�q�����ɍs���Ƃ܂��t���ς������ς��m�F�ł��܂����B�������H�����A�炢�Ă�I���������Ȃ̂ŏ�܂ŏオ���ĉ���Ă��č��x�͌I���ցB�����������ƍ炫�n�߂Ă��܂����B������ł��ˁB�����T�L�T�M�S�P�������B









�@�V�C���悭�g���Ȃ̂ŕ�Ƃ��ł����ł��B�c�O�Ȃ��琅�j���͋x�݂̓X�������悤�ł����i�Ηj���������Ƃ����\������܂����j�B





�@�����̃��[�g�ŁB�ѓ��ɏo���炷�������ɏオ�茎���R�֍s���A�A��͏Ҋ��r�����Ɠ�������Ă��܂��B���̂����肩�Ȃ��|����ɐ������Ă���悤�ł��B�@




�@��������Ə铇�͎𑠂т炫�������Ă��܂��B��P���̐悠���肩��l������n�ߑ��̎�O�܂Ń����b�N��w�������l�������Ⴄ��������A�V���g���o�X���s�������Ă��܂��B���̒����Q�������đ��蔲���܂����B
�@����̓V�G�}�ցA�u�ƂA�낤]�iThe Last Suit �j���ςɁB�ƂĂ������f��ł����B�A�E�V���r�b�c�Ƃ����ߋ��Ɛl���̏I��ɂ����������������B�d�������������ƕ`���Ă��܂��B���āA�l���������āA�����܂��A�z���g�ɁB�����č����͐��͔��p�قցB�W�߂ƌ����Ȃ����Ƃ��Ȃ�����Njt�ɑ��l��������A������܂�Ƃ��������Ȃ̂Œ��悢��i���ł������ς�܂��B�ǂ�����A�h��ł͂Ȃ�����ǁA��ې[���f���炵�����̂ł����B

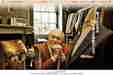

�@�ԓ���������h�_���e����オ��A���ՂŔ����R�[�X�ɏ��܂��B����ς蔭�S�͂����ł��B�ł������x���B�V�C�͂������lj���ł܂��ˁB�A��͍Ō�܂Ŕ����R�[�X������Ă��܂����B


�@�قڈꏏ�ɓo��n�߁A�Q�A�R�x����ւ��A���ǂقړ����ɓ����������������̏�ŕW�����C���B���傤�͉��x�̎�O�����R�ɉ���Ă݂邻���ł��B�V�O�O��H���Ȃ�̃x�e�����̂悤�ł����B

���{

�o������

����ł܂�

��{

����܁H
�@�V�C���悩�������A�C�������߂Ȃ̂ŁA�������Ǝv�������āB�S�̂�����Ƃ܂��Z���H������Ƒ������ȁA�ł��~�͑��߂ł��[��������A�悵�B






�P���R�P���i�j�F�J�̍���ƒ���̊X�i����`���R��`��R��j
�@�p�F�R�̖k�Ɉʒu���鍙��(363m)�B�߂��̊��Ƀ_���M�N�̍炭�Ƃ��낪����Ƃ����B�G�߂ł͂Ȃ�����ǁB�R���߂��̓W�]��܂ŎԂōs���܂��B����܂ł͍s���܂������A��������J�B���͒f�O���������炦�B���߂Ē��؊X�̋��؉��ɍs�����Ƃɂ��܂������A�Ȃ�Ƌx�݁B���F���Ă���ƍ]�R�O�ƌ����Ƃ��낪�悳���A����܂��B�����B�a�˂Ƃ����̂����������������A�\���݂ˎq���������A�Ƃ��ǂ��^��ł���~�[�̏����Ȃ�����������������A�d���̂ł���l����������̂͋C���������ł��ˁB
�@���Ƃ̓I�����_�₩�瓌�R��̗m�ٌQ���Ԃ�Ԃ�ƌ��ĉ��܂����B���F�n�ƌÎʐ^�����̓W���ق��ʔ��������B�O���o�[���̓p�X�B�������ɓ犥�R(169m)�ƌ����̂�����̂ōs���܂��B�W�]�䂩���Y�V�哰���^���ɁA�����Ē���`�̌����Ɉ�R�A����ɏ��_�勴�A�E��͋��䗅�R�A���C�R�A���R�������ΎR�A�����R�A�����ĉp�F�R�A�����R�B�����A�����R�̃����c�������ƁB�����ł��ˁB�A��͓r��������Ǝԓ����O��ėV�����炵�������Ƃ�����A���̂������̒��̓��ɂȂ�A�l�̗���݂����ȂƂ����ʂ�A���`���肾���B��Y�V�哰�͊O���璭�߂邾���ɂ��܂����B

���ѐ_��

��������J

������

�f�O

���؊X

�a��

�U�����܂�

�m�ٌQ

����Ⴀ�ԂȂ�

�犥�R����

����čs���܂�

��Y�V�哰

���������܂�
�@����ɓV�C�͉̗\��B���ǎR�n�̒����ȎR�X�Ɉ͂܂ꂽ�n���ȎR�B�D�݂ł��ˁB��������܂����b�x�ցB500m���̂Ƃ��납��傫�Ȓ������������ăX�^�[�g�ł��B�T�����œo�R���B�R�O���Ŕ����̈ƕ��B�E�̃s�[�N���b�����x�V�{�܂łT���B����֖߂��č��̃s�[�N�����܂��B�X�͂���܂����Ȃ��Ȃ��ǂ������̔����ł��B�Q�T���ʂŁA�������[�I���₢��j�Z�s�[�N�ł����B�ł��W�]�̂悢���ŁA��������Ɛቻ�ς����o���x���瑽�NJx�֑����Ő��������܂��B�R���͂������傢��ł����B�W�]�͂���܂���B��ԎR����܂Ŗ߂�A���x�͓��x���߂����܂��B�U�R�Om�̎l�҂܂ʼn��肽���Ƃ͓o��Ԃ��ł��B�S�̃s�[�N���z���T�ڂ����x�B�ӂ��B���[�����ƍ�������Ă������V�Ղ�O��ł��邭�����ɂ��܂��B���R�͂P�O�����Ŏԓ��ɏo�āA���Ƃ͎ԓ����R�O�������ăS�[���B

�傫�ȓS������

���b�����x�V�{

�o���x

���b�x�̃Q�[�g

�{���̂����ɁH

�؎��A����Ƙ@���V
�@�_������܂ōs���܂������A���̎�����������܂���ł����B�܂����Ă��܂��܂����B����ȓV�C�̗ǂ����ɂ���Ȍ����ցB




�@����������ɋC�����������͗l�̓V�C�ɂȂ�܂����B�����͔Z���łQ�A�R�Om���炢�������E������܂���B�����͉��₩�ȓV�C�ŋC�����オ�肻���Ȃ̂ŋ}���ōs���܂��B�Ԃɍ����܂����B���R���Ă���Ƃ��̏ォ��������Ⴊ�J�̂悤�ɍ~���Ă��܂����B





�@�ŏ��͉̂_��Ȃɕ��z���錴��^�C�v�������ł��B�ł�����ς�̏��n���D���ł��ˁB���i�̍ŏ��͑��Y���ҁB�l���ڂ͌Ӓ��̏��A���͐����������̂ł��B�A��̃o�X�܂Ŏ��Ԃ��������̂ŋ߂��ł�����H�ׂċA��܂����B�ׂɂЂ��H�ׂ��킯����Ȃ��ł���B���A�Ō�̂͋����ւƌ��������ł��B���̎��������Ă���炵���������A�ƌ����Ă��W�O�ゾ�낤�A����Ȃ̂������ƈē����Ă���āA�}���Ƃ�����炭����܂��Ă����Ă��ƌ����Ă��ꂽ�̂ʼn����Ȃ��A�ۂ���ƁB












�@���x�͓o��Ɏg���Ă݂܂����B����ς肿����Ɠr���킩��ɂ��������O���܂����B���R�܂ōs���āA�����R�o�R�ʼn���Ă��܂����B���҂ǂ�����͎��Â�����Ă��܂����B�悩�����ł��B��J�̓����̃~�c�}�^���}���T�N���炫�n�߂Ă��܂����B






�@�܂����C�����ł��B���āA�l������ς肱�̖{�ɛƂ�܂����ˁB���R���̉f��̂��ƁA��f����Ă��邱�Ƃ�m��ςĂ��܂����B�u���C�����ł��܂��āv�����܂ꂽ�w�i�����߂Ēm��܂����B

�@���E�o�C�����łȂ��A���̊Ԃɂ��g�~���炢�Ă��܂��B

�@�����R�̓����t�߂Ɍy�g�������䂢�āA�Ҋ��r�̏�̂�����肵�Ă���l�q�B���̎��Â����Ă����̂ł��傤���B���傤�͂�������������L�����Ƃɂ��܂��B�܂��Ȃ����R���ȂƂ���������A�����ƌÂ����ȕW��������B�h�����āu���Ή����v�Ɠǂ߂�B���Ⴀ�Ҋ��r���̗ѓ��ɏo��ȁB�s���܂��B�ŏ��̕��͍L���ė��h�ȓ��B���̂�������C���ɂȂ�܂��������ݐՂ͂���܂��B�o���B����A���Ή���̎�O�ɉ���Ă��܂����B




�@�܂��s���܂����B�_��ɔ������ɍs�������ƁA�ŒZ�̕S�ԐΊ_����B���X�����A����ʏ`�����̒��ōL���肻���ł��B�F����������s���Ă悩�����ł��B���ɕ{����͂܂��ʍs�~�߂ł����B���ԂȂ����ԂȂ��B






�@�U�O�ŖS���Ȃ��Ă��܂��B�Ȃ�Ƃ����������Ȃ��B



�@�e�R���o���B�������͋C�̂��������쉈���̗V������i�݁A���������n��Ƃ��炭�ѓ������B�I�_����o�R���B����낿���Ɛ��������C���̂��������ȑ�������A�J�𗣂�}�Ζʂ��オ��Ɣ����B����ɋ}�o��o���čr���R�R���B��Ղł��B�}���~���ƕ��ɍ~��A�}�ȍ����o��Ԃ��ƌX���ɂ݂܂��B���炭�s���Ƃ܂��܂��������o��B����ƂS�R�X�̃s�[�N�ɒ����B���肪�������Ƃɂ���������R�ւ͎v������葁�������܂����B���������Ȃ̂Ŏs���̐X�ւ͉��肸�ɁA�k�ɑ�������������čs���܂����B������A�T�U�X�D�R�̃s�[�N�A������A�ԓ��ɏo������R�ω��Ɋ���āA�o�X��͂ǂ����ƁA�Ă��Ă������܂����B���R�͂������萮�����ꂽ�s���̎R�ł��ˁB

����������

��厩�n�̒n

�r���R

�R������ҐU�R�n

���R����\������

���[�g�}�b�v

������

������

�v���������R����

�ω��l
�@���R�ɂł��s���Ă݂悤���Ɠd�Ԃɏ��܂����B�Ƃ��낪���S�ŗՎ���Ԃ��A�s�{�O�E���嗘�ԂŐl�g���́A����s�܂ł̐܂�Ԃ��^�]�A�ƕ����������B����͎l�����ɍs���Ƃ������Ƃ��ȁB
�@�Ȃ̂ő��ɕ{�܂ōs���A�܂����r�R�ɍs���A�����Ƃ͋t�ɍ����B�匴�R���߂��A�P�V�ԎD�������Ɍ��āA�����ɂ̓Z���o�I�E�����������Ȃ��B�܂Ă�A����ŌQ���������̂͊������A������E�E�E�A�s���|�[���I
�@���Ƃ͏��Ί_�̕�����S�ԐΊ_�A���R�A��{���[�g�Ő����Ղɉ���Ă��܂����B�������T���h�C�b�`���Q�b�g�B���łɓV�Ղ���B










�@�������O�x�ځB���₩�ȓV�C�Ȃ̂ŕ����čs���܂����B���̓��ł͂���܂�������[�߁B�����̌��j���B�܂������ƌ����ׂ����A�����Ԍ������ƌ����ׂ����H




�@�����͐悸�g���x�ɍs���܂��B�Օ��_�Ђ̐��A�O�m�ȗւ֏��߂čs���Ă݂܂����B���߂��悢�B�m��Ȃ������B���ꂩ�獂�Ǒ�ЁB�l�������ł��B�����āA����r���������c�́i�w�������j��������������ˁB���ɔ���������Č����R�B�����H�ׂĔ�����x�ցB���m�@�����ʃR�[�X�ŁA�������h�m���x�ɂ���ĉ���Ă��܂����B

����ł܂���

������

�Օ��_��

������Ă܂�

���m�@

�h�m���x
�@���͓V�C���悩�����̂ł����������ɂ͉_���L�����Ă��܂����B���Ǒ�Ђ̓쐼�ɘh�m���x�Ƃ����������s�[�N������̂ōs���Ă݂܂����B�Q�Q�Rm�قǂ���悤�ł��B���̂܂ܐ��ɐi�ނƎԓ��ɏo�܂��B�g�t�J�ŎQ���ɖ߂�܂����B

����������

�L���C����

�������

�p�F�R����

�����R

�V��������